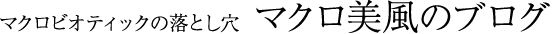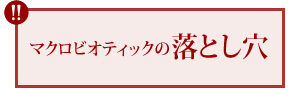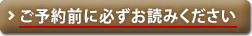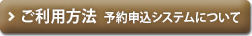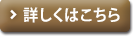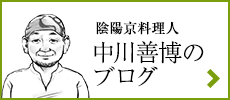先日の幸せコースの食事日記で、素晴らしいお食事内容を記載しておられた“じゅんじゅん”さんですが、ご本人は「とても不完全で、このままの食事内容だと私はどうなってしまうのだろう?」と思っていらっしゃるようです(笑)
完璧主義者なんですね。
でも、ご本人は全然そんなふうに思っておられません。
ご自分はダメダメ人間だと思っておられるのですから、面白いものです。
そんなことはありません。
じゅんじゅんさんはとてもキチンとしていて、お料理の復習投稿でも完全な投稿をされます。
見事です。
でも、食事日記の最後に気になる文章がありましたので、記事でアドバイスをさせていただきます。
夕食の時間帯について、似たような環境の人がたくさんいらっしゃると思うからです。
>もう一つ、ご指導いただきたいのが会社での食事時間です。
>昼の休憩が12:20から1時間、夕食の時間が17:10から30分。
>残業時の食事はこの時間になるので、昼食のご飯を少なめにしていますが、17時に夕食を食べ、21時に帰宅すると何か食べたくなり、食べ始めるとあるだけ食べてしまいます。
* * *
残業しても帰宅が21時って、東京ではそんなの残業とは言わないくらいですね(笑)
17:10からのお食事は、しっかりしたお弁当を持参しないで、おにぎりを1個〜2個にしましょう。
そして、帰宅したらおかずの残りとか、ウエットなおかずとか、スープ類を飲めばそれでOKです。
それらがない時には、簡単にできる麺類にしましょう。
とにかく汁物を摂ることがポイントです。
汁物の陰性が疲れを癒やしてくれるからです。
「一日に2回同じものを食べたって平気!」というくらいの気持ちでいないと、あなたはついつい完璧を目指してしまうので、窮屈になってしまいますよ。
残業は毎日ではないので、このくらいの気持ちで陰性の食べ物を楽しんでください。
そうでないと陽性に苦しめられることになります。
おにぎりも陽性になるので、夜はなおのこと陰性を意識して召し上がってください。
完璧主義(陽性)だと自分も周りもつらくなります。
ほどほどに緩め(陰性)ましょう。
マクロビオティックの陰陽を知った今なら、それができますね?

(松茸 マクロビオティック京料理教室 むそう塾 )
きのこはあなたに召し上がっていただきたい食材です。
これから沢山のきのこが出回りますから、毎日ムシャムシャ召し上がってください。
+ – + – + – + – + – + – +
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
・「2018年度(第10期)幸せコース」授業日程のご案内
・中川式糠床受付方法のご連絡(2017年度の場合)
・中川式糠漬け(じゃい安)のご注文案内
・中川式鉄火味噌のご注文方法
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
・中川善博厳選!おすすめ器具と食材