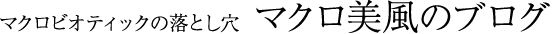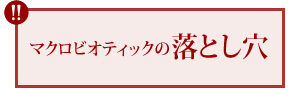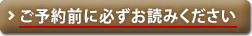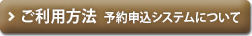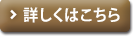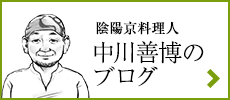ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- これから開催予定の講座案内(2026.1.22現在)
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)
- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ
- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?
- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内
- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ
- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在
- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内
- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)
- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」
- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著
- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能
- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内
- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて
- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!
- ポリファーマシー(多剤服用)の心配
- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと
- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた
- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから
- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん
- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます
- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内
- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内
- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内
- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内
- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内
最近のコメント
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より
カレンダー
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
カテゴリー
- 講座のご案内・連絡事項 (1,223)
- 健康情報 (2)
- 新しいむそう塾 2022年 (28)
- 料理は呼吸と同じ (24)
- うれしかったこと (198)
- 玄米の炊き方講座 (216)
- お弁当の想い出 (6)
- 京料理人 中川善博の動画 (83)
- 京都やマクロビオティックのことなど (208)
- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)
- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)
- むそう塾スタイル (51)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)
- 食べたもののようになる (107)
- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)
- 中川式糠漬け (269)
- 中川式出汁巻き玉子 (24)
- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)
- 幸せコース感想文 (36)
- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)
- 子育て・野口整体・アトピー (308)
- 男子厨房に立つ (17)
- 新型コロナウイルス (133)
- からだ (561)
- こころ・想い (533)
- 食べ物あれこれ (338)
- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)
- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)
- 陰陽ひとり立ち講座 (93)
- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)
- 体験談 (134)
- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)
- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)
- マクロビオティックと歯科治療 (24)
- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)
- 本の紹介 (121)
- その他 (208)
- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)
- マクロビオティックわの会 (9)
- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)
- むそう塾 パスポート発表 (204)
- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)
- ワーママさんの応援 (4)
- 中川善博の入院日記 (12)
- HP記事更新のお知らせ (9)
- 夫の病気関連 (9)
macro88のtweet
-
「マクロビオティック京料理教室 むそう塾」カテゴリーアーカイブ
京料理人 中川善博が教える栗の皮むき コツのコツ(動画付き)

(栗ご飯 料理:京料理人 中川善博 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)
栗の美味しい季節になりました。
しかし、自分で栗の皮がむける人ってなかなかいませんね。
むそう塾の幸せコースでは栗の皮むきも教えていますが、授業中に撮った動画がありますので公開します。
【栗の皮むき(1)】
[youtube width=”660″ height=”440″]
【栗の皮むき(2)】
[youtube width=”660″ height=”440″]
いかがですか?
幸せコースで習った人はもちろんですが、過去に習った先輩でも見落としているかもしれない重要なポイントを、包丁に赤い印をつけて公開しました。
栗の皮むきの基本は、大根の桂剥きにあります。
桂剥きで剥く基本を教わって、その土台の上に栗の桂剥きが成り立つのです。
美味しい栗ご飯のために、頑張ってください!
+ – + – + – + – + – + – +
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
カテゴリー: 京料理人 中川善博の動画, マクロビオティック京料理教室 むそう塾
コメントする
食べ方は生き方そのもの
やっと3クラス分の食事日記の添削が終わりました。
連日パソコンに向かって、長時間Excelの画面を見続けるのは、68歳の年寄りには大変な作業ですが、一字一句漏らさず読み切りました。
そして、確実にポイントをお伝えするため、Wordで感想とアドバイスをお一人ずつ書きました。
あとは塾生さんがそれを実行出来るかどうかです。
私は実行不可能なことは記事にもしませんし、塾生さんにも言いません。
机上の空論も振りかざしません。
すべては体験したことや、周りで経験した人がいる内容を書いています。
ですから、本人がやる気になって挑戦してくださったら、確実に答えが出るものだけをアドバイスに書きました。
それも相手の実行度を踏まえた上で。
よくマクロビオティックの食事指導で経験することですが、相手の性格や行動力を無視して、理想の組み合わせを一方的に伝えるだけの指導者がいます。
そうするとどうなるかというと、結果が出ないだけでなく、本人もとてもつらくなってしまい効果が出ません。
病気で命がかかっていても、なかなか実行しない人もいるのが人間というものです。
いかに実行してもらうか?
それには相手の陰陽はもちろん、考え方や生き癖まで把握しないと無理ですね。
誰しも嫌なことや面倒なことはしたくないものです。
仮に命がかかっても嫌なことには手を染めないで生きようと思う人が多いのも事実です。
多くの人の食事日記を見て思うのは、食べ方は生き方そのものということです。
空腹を満たせれば何でも良いのではなく、そこにマクロビオティックの陰陽をからめて食材やお料理方法を選べば、あなたの体はもっと処理能力が上がります。
そのコツをお伝えするべく、まずは食べ癖と体の反応をチェックするのが食事日記の添削でした。
そんな自分を踏まえて、これからどんな自分になりたいのか?、どんな生き方をしたいのか?、それを実行段階に移すのが今日からです。
生まれ変わるのもよし、そのまま突っ走るのもよし。
ただ、一つだけ伝えておきたいことがあります。
それは、主食がしっかり入っている人は底力があって、精神的にブレていない人が多いことです。

(京都産 松茸)
幸せコースの10月授業は、松茸ご飯と栗ご飯です。
高級料亭の一番出しの取り方も伝授します。
松茸ご飯は玄米で、栗ご飯は白米で炊きます。
玄米でふっくらした炊き込みご飯を作るのは、とても難易度が高いのですが、中川式は陰陽をとことん研究した炊き方なので、白米と同じように美味しい玄米松茸ご飯が炊き上がります。
他のマクロビオティック料理教室で、玄米の炊き込みご飯を習ったことのある人には驚きの炊き上がりです。
+ – + – + – + – + – + – +
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾, からだ
コメントする
マクロビオティックの食事日記 「人の運命は食にあり」
私は常々望診をしていますから、相手を見ると日々の食べ物が想像できます。
水分量の多寡や、甘いものの好き嫌いなども手に取るように伝わって来ます。
この望診力はやはり数をこなすことで一層精度が上がりますので、塾生さんと深くおつき合いさせていただいて、何年も観察していると、食べ物の力の怖さみたいなものを感じます。
ですから、先人が食べ物に着目したのも頷けますし、水野南北の「人の運は食にあり」というのも納得できるのです。
水野南北は江戸時代の観相家ですが、彼の考え方は食養の石塚左玄にも影響を与え、当然のことながらマクロビオティックの創始者桜沢如一にも影響しているのです。
そしてまた私も、水野南北が残した人体実験や、食べ物に対する洞察には少しずつ頷けることが多くなってきました。
水野南北は食事と開運を結びつけた人ですが、今の時代にそのまま当てはめることは出来ないにせよ、少なくてもマクロビオティックの判断力とはリンクしているのを感じるのです。
あなたが口にする食べ物が、あなたの人生と運を左右すると知ったら、少しは真剣に食べ物のことを考えてみようかなと思われるのではないでしょうか。
私がむそう塾で食事日記をつけてもらうのも、塾生の皆さんが食べ物の力を知って、少しでも良い方向に歩んでいける力を自分でつけられるようになってもらうためです。
昨日も素晴らしい食事日記が送られて来ました。
主食がその人の中心軸を作ると常々思っていましたが、やはり主食がきちんと確立している人は心身両面で強いです。
特に精神面の強さを主食は育ててくれますね。
そんなことを感じながら、私の食事日記添削は延々と続きます。
結構気の遠くなる作業ですが、頑張ります!

(京都 無鄰菴)
京都はそろそろ秋の変化を見せ始めました。
これからどんどんと木々の表情が変わってきます。
私たちも同じように食べるものを変えて行きましょう。
食べ物の衣替えの季節です。
+ – + – + – + – + – + – +
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
マクロビオティックの食事日記と判断力の7段階
ただいま「むそう塾幸せコース」恒例の食事日記を添削しています。
丁寧に、実に丁寧に隅から隅までチェックしています。
それは頑張って記入してくださった塾生さんへの礼儀でもありますし、食べ物が体に及ぼす影響を現実的に確認するためでもあります。
つまり、私自身も勉強になりますし、私の望診力も上がるのです。
ですから、真剣に一字一句読ませてもらっています。
マクロビオティックではよく「食べたもののようになる」といいますが、まさにそれを実感するのがこの食事日記です。
食事日記をつけていただく目的は、ご自分でご自分の心身をコントロールする一つの方法として、食べ物の力を知ってもらうためです。
よく「変わりたい」とか、現状の不満を口にされる方がおられますが、ただ思っているだけでは何も変わりませんし、不満も解決しません。
それを誰かに変えてもらうのを待つのではなく、自分の力で変えていけることを説いているのがマクロビオティックの陰陽を用いた食べ方や考え方です。
* * *
例えばお酒を毎日大量に飲む人がいたとします。
人間はそんなに大量に毎日お酒を飲まなくても生きて行けるので、その理由を知ることも大切なことです。
なぜなら、毎日続けて摂るものは確実に心身に影響するからです。
楽しくてお酒を飲みたいのか?
気を紛らわせたくてお酒を飲みたいのか?
これだけでも陰陽では真逆になります。
あるいは何となく水分が欲しくて、それがたまたまお酒だったということもあるでしょう。
じゃあ、その前にどんな食べ物を食べたのかな?
すごくそれを食べたかったのかな?
それはどんな味付けだったのかな?
そんなことまで考えていくと、あなたの心の中まで透けて見えてくるんですよ。
そのツールがマクロビオティックの陰陽です。
ですから私は、そのツールを活かしてご自分を知る方法を幸せコースで教えようとしているのです。
そして、ご自分でそのツールを使いこなせるように、その練習をするのが9月と10月の幸せコースの座学内容です。
ただ単に食べたいから食べるというのでは、マクロビオティックでいうところの判断力が最低のところですね。
過去記事で「マクロビオティックの判断力の7段階」について書いていますので、ご参考になさってください。
「マクロビオティックにおける判断力と食事」
もっと詳しく知りたい方は日本CI協会の「判断力の7段階」がありますが、難しいかな?
そんなに難しく理屈をこねたくない人は、ただ単に「体に良くて美味しいものを食べる」と端折ってもかまいません。
頭でっかちで食べるのはかえって悪いのでね。
しかし、むそう塾生なら、コントロール術だけは身につけてほしいなと思います。

(蛸飯 料理:京料理人 中川善博 マクロビオティック京料理教室 むそう塾)
陰陽をよ〜く考えて作られたこの蛸飯は、やみつきになる美味しさです。
山椒の実も陰陽を考え抜いた作り方なので、こんなに沢山載せてもOKなのです。
陰陽って凄いですねぇ。
+ – + – + – + – + – + – +
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
玄米の炊き方秘伝(第100回愛クラス)が終わりました
昨日は第100回めの玄米の炊き方講座(愛クラス)を開催しました。
むそう塾の基本中の基本講座であり、新しい人が受講できる唯一の講座です。
昨日ご参加くださったのは、青森1名・埼玉1名・東京1名・石川1名・京都1名・大阪1名、新人さん4名・再受講者2名という内訳でした。
2008年に第1回めを開催してから丸8年、多くの人がこの講座を受講してくださって、100回めを迎えることができましたことに、心から感謝を申し上げます。
受講してくださった皆さんのお顔が次々と浮かんで、皆さん、どうされているかなぁ、ちゃんと玄米を食べていてくれるかなぁと想いは尽きません。
年月とともに物事はずれていくものですが、昨日はすでにパスポートをお持ちかたがパスポートを返上して最初からやり直したいと決心して、新しい塾生番号とともにもう一度愛クラスを受講してくださいました。
帰るところがある幸せ。それを実感してくださったようで、とても心穏やかな満ち足りた時間を過ごしてくださいました。
人生の新しい展開も始まって、彼女のこれからにエールを送りたいと思います。
むそう塾のサイトはネット上に建てられたみんなの家です。
そこのお茶の間がむそう塾という教室で、語り合う手段としてマクロ美風のブログや中川善博のブログやそれぞれのTwitterがあります。
顔を見たくなったらいつでも京都の教室にいらしてくだされば良いのです。
鴨川を見て懐かしさがこみ上げてくることでしょう。
人生を考え、恋愛を考え、健康を考え、仕事を考え、人づき合いなどを考え、諸々のことを「食」という一点から調整しようとする場所です。
そこにこうして多くの方が「帰る場所」として集えることを、とても有り難く思います。
昨日再受講してくださったおはるさんは、愛クラス最多受講者ですが、何度受講されても幸せを感じてくださって、ほっこりした表情をされます。
まさに彼女にとってもむそう塾は帰る場所であり、愛クラスはその原点になっているのです。
心のすべてを共有しながら歩んだおはるさんとの8年以上の歳月を、感慨深い思いで受け止めました。
彼女の表情の何と柔和なこと。
紆余曲折を経て、あの表情が出来るようになったことを、家族の一員として安堵しています。
* * *
お顔はその人の領収書です。
どう生きて来たか、それが全部お顔に表れます。
一番表れるのは目ですね。
涼やかな目、吸い込まれるような笑顔、それを保証するのはあなたの血液です。
自分の体にどんな血液を流したいか。
その血液でどんな体を作り、どんな生き方をしたいか。
あなたの人生はあなたの食べ物で出来上がって行くのです。
現状に不満がある人は、まず食を見直してみましょう。
お料理が出来ない人は、まずご飯だけでも炊ける人になりましょう。
そうすればグーーーン!と世界が変わります。
すべては陰陽バランスの上に成り立っています。
物事がうまく行かない人はバランスが崩れているのですから、そのバランスを立て直せば良いのですが、その原点は陰陽の考え方を知ると嘘のようにスルスルと解決します。
むそう塾でお教えしている玄米ご飯の炊き方は、一般に伝えられている炊き方とは異なりますが、私が知る限り最も陰陽を忠実に反映した炊き方です。
なぜ中川式玄米ご飯はこんなに美味しいのかと問われたら、すぐさま「陰陽に忠実な炊き方だから」と答えます。
そしてその方法は、人生にもピタッと当てはまるのです。
陰陽に忠実な生き方。
それがあなたの健康と幸せを可能にしてくれるのです。
むそう塾のお料理はすべてマクロビオティックの陰陽で洗い直してありますので、どのお料理も陰陽に忠実に作られています。
ですから、それを召し上がった人が穏やかな気持ちでいられるのです。
人生は難しく考える必要はありません。
自然に笑みがこぼれる時間を過ごすこと。
これに尽きます。

(教室の掛花 マクロビオティック京料理教室 むそう塾 2016.9.25)
* * *
【ご案内】
・これから開催予定の講座案内 最新版
【サイト内の記事】
・マクロビオティックの盲点
・塾生のきょうの100点お弁当
・陰陽を感じる日々の暮らし
・中川善博から娘へのお弁当
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾, マクロビオティックが楽しい♪, こころ・想い
6件のコメント