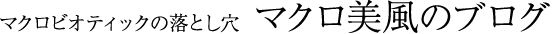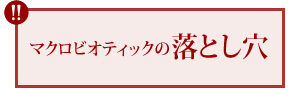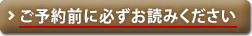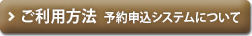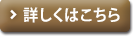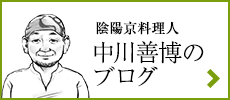「むそう塾 幸せコース」の7月のメニューは麺三昧でした。
冷たい麺はもちろんのこと、温かい麺も二種類伝授しました。
「カレーうどんは男性に喜ばれますよ?」という中川さんの言葉に促されてかどうか、帰宅してからその日のうちにカレーうどんを作った人の何と多いことか!
その後も続々とカレーうどんの報告が届き、皆さんやはり男性陣に喜んでもらえたと、嬉しそうに書いてくれました。
きょうもNさんからカレーうどんのメールが届きました。
一時はうまくいかなかったご夫婦ですが、これでもう安心。
二人でカレーをすすって、いい汗をかいてね。
ところで、中川さんが作るお料理が男性に喜ばれる理由は良く解ります。
つまり「男の味」なんですね。
決して女性の自己満足の味ではないんです。
メリハリのあるキレのいい味とでもいいましょうか。
私も試食しましたが、確かに中川さんの「カレーうどん」は抜群の美味しさです。
一般的にお饂飩(うどん)屋さんで出てくるカレーと比べて、はるかに美味しいと私も感じています。
う?ん、お見事!
* * * *
<Nさんからのメール>
昨日、主人が休みだったので、カレーうどんを作り一緒に食べました。
汗をかきながら二人ですすっていたら主人が「熱いね!」と一言、そしてしばらくして「美味しいね」と言ってくれました。
「わ?うれしい?」とおもわず子どものように喜んでしまいました。
あまり「美味しい」と言わない人なので・・・。
お教室では満腹でできなかった「残ったカレーつゆに玄米御飯」もできて大満足でした。
幸せコースで教わったお料理を、実際家で作ってみると、教えていただいたことの素晴らしさを改めて感じます。
一つ一つの工程の意味、そして意味の無いことは一切ないこと、自分で実感し、家でもう一度感動しています。



ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた
- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから
- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん
- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2025.12.3現在)
- これから開催予定の講座案内(2025.12.2現在)
- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内
- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内
- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内
- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内
- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内
- 「2026年度(第7期)自由人(びと)コース1」受付開始のご案内
- 「2026年度(第12期)秘伝コース」受付開始のご案内
- 「2026年度(第18期)幸せコース」受付開始のご案内
- 鉄火味噌が出来上がりました 節多め 筍入り
- 年越し蕎麦(晦日そば)セットを限定販売します
- 化学肥料、農薬不使用栽培玄米餅の「京あもさん」が販売開始!
- 「偽善医療」藤井聡・木村盛世著
- 商売のコツはモノを売るな癖を売れ コーヒーの成功例
- 育てられ方は一生を支配する 恐ろしいほどに
- 「デキル女性」は受講上手 復習上手
- 夫の病院通いは間隔が空きました 富士山に励まされた日
- 再開催ご希望講座一覧(2025.11.21現在)
- 陰陽京料理人中川善博が焼いたフランスパンの食感に感動!
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー
- 「塾長蕎麦」をお宝さんDIRECTで全国の塾生さんへ!
- 「第9回 小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」開催のご案内
- 「第8回 小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」開催のご案内
- 丸八製茶場の「献上加賀棒茶」と「加賀ほうじ茶」が美味しかった
- 「スポット受講」ご希望者一覧 2025年11月8日現在
最近のコメント
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2025.12.3現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2025.12.3現在) に 佐藤美奈 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2025.12.3現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2025.12.3現在) に 佐藤美奈 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2025.11.21現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2025.11.21現在) に ここ より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より
- 京都・瓢亭さんでの課外授業を終えて に マクロ美風 より
- 京都・瓢亭さんでの課外授業を終えて に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2025.11.21現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2025.11.21現在) に 好 より
- 夫の病気と私のスケジュールは陰陽そのもの に マクロ美風 より
- 夫の病気と私のスケジュールは陰陽そのもの に 牧野はるみ より
カレンダー
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
カテゴリー
- 講座のご案内・連絡事項 (1,218)
- 健康情報 (2)
- 新しいむそう塾 2022年 (28)
- 料理は呼吸と同じ (24)
- うれしかったこと (198)
- 玄米の炊き方講座 (216)
- お弁当の想い出 (6)
- 京料理人 中川善博の動画 (83)
- 京都やマクロビオティックのことなど (207)
- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)
- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (430)
- むそう塾スタイル (51)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,197)
- 食べたもののようになる (107)
- 料理人 中川善博の陰陽料理 (175)
- 中川式糠漬け (269)
- 中川式出汁巻き玉子 (24)
- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)
- 幸せコース感想文 (36)
- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)
- 子育て・野口整体・アトピー (308)
- 男子厨房に立つ (17)
- 新型コロナウイルス (133)
- からだ (561)
- こころ・想い (532)
- 食べ物あれこれ (338)
- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)
- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)
- 陰陽ひとり立ち講座 (93)
- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)
- 体験談 (134)
- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)
- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)
- マクロビオティックと歯科治療 (24)
- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)
- 本の紹介 (119)
- その他 (206)
- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)
- マクロビオティックわの会 (9)
- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)
- むそう塾 パスポート発表 (204)
- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)
- ワーママさんの応援 (4)
- 中川善博の入院日記 (12)
- HP記事更新のお知らせ (9)
- 夫の病気関連 (7)
macro88のtweet
-