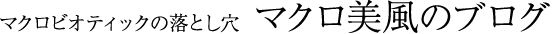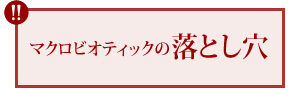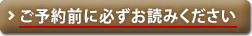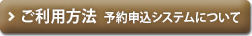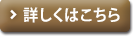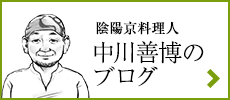ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- これから開催予定の講座案内(2026.1.22現在)
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)
- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ
- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?
- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内
- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ
- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在
- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内
- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)
- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」
- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著
- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能
- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内
- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて
- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!
- ポリファーマシー(多剤服用)の心配
- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと
- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた
- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから
- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん
- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます
- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内
- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内
- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内
- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内
- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内
最近のコメント
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より
カレンダー
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
カテゴリー
- 講座のご案内・連絡事項 (1,223)
- 健康情報 (2)
- 新しいむそう塾 2022年 (28)
- 料理は呼吸と同じ (24)
- うれしかったこと (198)
- 玄米の炊き方講座 (216)
- お弁当の想い出 (6)
- 京料理人 中川善博の動画 (83)
- 京都やマクロビオティックのことなど (208)
- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)
- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)
- むそう塾スタイル (51)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)
- 食べたもののようになる (107)
- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)
- 中川式糠漬け (269)
- 中川式出汁巻き玉子 (24)
- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)
- 幸せコース感想文 (36)
- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)
- 子育て・野口整体・アトピー (308)
- 男子厨房に立つ (17)
- 新型コロナウイルス (133)
- からだ (561)
- こころ・想い (533)
- 食べ物あれこれ (338)
- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)
- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)
- 陰陽ひとり立ち講座 (93)
- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)
- 体験談 (134)
- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)
- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)
- マクロビオティックと歯科治療 (24)
- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)
- 本の紹介 (121)
- その他 (208)
- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)
- マクロビオティックわの会 (9)
- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)
- むそう塾 パスポート発表 (204)
- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)
- ワーママさんの応援 (4)
- 中川善博の入院日記 (12)
- HP記事更新のお知らせ (9)
- 夫の病気関連 (9)
macro88のtweet
-
「マクロビオティックの指導現場からシリーズ」カテゴリーアーカイブ
マクロビオティックの指導現場から(11)不妊と生殖医療
こちらの記事の私のコメントに関連して、てんこさんが不妊治療に関する文章を寄せてくださいました。
実は、この不妊治療を陰陽で判断すると、ある治療はとても大きな問題点があるのですが、社会的影響を考えてずっと伏せていることがあります。
私は不妊治療の研究者ではないのでなおのことです。
現在はこちらの記事にもありますように、不妊が生殖ビジネスとして暗躍している現実もあります。
簡単に生殖ビジネスに乗ってしまう前に、考えるべきことはたくさんあります。
そのことに一人でも多くのかたが気づいてほしいです。
まずはその文章からお読みください。
<てんこさんの文章より>
先日、『生殖医療の未来』と題した講演がありました。
生殖医療は不妊治療と言い換えてよいかと思います。
不妊で悩まれている方は年々増えていますので、感じた事をお伝えしてみたいと思います。
生殖医療は晩婚化に伴って需要が増していますね。
一番最近のデータでは1年間に生まれた赤ちゃんの約3%(約3万人)が生殖補助医療によって誕生しているそうです。
欧米では4%に達しており日本もいずれそうなるだろうというお話でした。
私の印象では高齢妊娠の方だけでなく20代のご夫婦でも不妊治療をされて妊娠した、という方達が増えているように感じます。
不妊という言葉の抵抗感が減っているかもしれません。
だとしたら、怖い事です。
妊娠しにくい事が重大な問題ではなく、ごく普通の事になってしまったら。。。。
今回の講演では卵子提供の話題が取り上げられていましたが、いずれにしても生殖医療の目的は不妊状態にある体を自然に妊娠できる体にすることではなく、いかにして妊娠させるか、いかにして生児を得るか、という点に尽きると思います。
そこには、その命がどのような環境で育ち誕生したのかという視点がすっかり欠落しています。
どのような環境でその命が育まれたのかにより、その命が内包した陰陽バランスが決定づけられます。
自力では妊娠できなかった人に薬物を使って妊娠を成立させ、その結果誕生した命は、いったいどんなものを背負っているのでしょうか?
不妊の因子は女性因子、男性因子、その他に分けて考えられています。
例えば卵巣機能が悪くて排卵しないために不妊だとしても、排卵するパワーがないほど陰性な場合と、陽性すぎてガチガチになっていて卵子を排出ができない場合が考えられます。
また排卵していても陽性が強すぎて受精卵を受け入れる事が出来ない方も居るかもしれませんし、陰性で受精卵を保持できずに妊娠維持できない方もあるかもしれません。
男性の不妊因子は主に精子の問題になりますが、具体的には精子の数が少ない、運動能が低い、奇形が多いなどの状態があります。
どれも陰性な状態です。
このように陰陽理論で捉えてみると、その陰陽バランスを見極め改善してあげれば、自然な妊娠が期待できるのではないかと推測することができます。
妊娠させるのではなく、出来る体をつくることが目標であるべきです。
現実には生殖医療で誕生した命がたくさん存在します。
その方達を否定するつもりはなく、陰陽のエネルギーの元に誕生する事ができた命なのだから、その命たちも宇宙の法則を思い出してそれに沿うように生きてくれたらいいな、と思います。
不妊治療を受ける事は、金銭的・時間的・精神的・肉体的に大きなストレスを生みます。
そんなストレスいっぱいの状態で妊娠した場合と、健全な性生活によって妊娠した場合では、その後の妊娠生活もお産も育児も大きく違ってしまうでしょう。
ですから、マクロビオティックが提唱する食事方法を利用して、健全な命を育めるたくましい男性・女性が増えてくれることが、いかにして他人から精子や卵子を提供してもらうか考えるよりずっと大切な事だと思います。
そうしないと、次世代はもっと深刻な不妊に悩まされるのではないかと心底危惧しています。
<マクロ美風より>
私も不妊治療の記事を過去に書いていますので、てんこさんのスタンスはよく理解できます。
一つだけ私から加えさせていただくなら、今は男性も女性も体が冷えている人が多いです。
その大きな理由は、すでに母親の胎内にいた時まで遡る必要があるでしょう。
妊娠前から母親や父親の食べていたもの、そして妊娠期の母親が食べていたもの、冷房や服装を含む暮らし方の問題。
それらを前世代まで遡って考えたうえで、今まさにお子さんを希望される人達の陰陽バランスを整えることが根本的な解決につながると思うのです。
それは食べ物だけでなく、環境を含めてもっと大きな問題として取り組むべき課題ですから、体が冷えるということは、今や国民病といっても過言ではないと思います。
>このように陰陽理論で捉えてみると、その陰陽バランスを見極め改善してあげれば、自然な妊娠が期待できるのではないかと推測することができます。
>妊娠させるのではなく、出来る体をつくることが目標であるべきです。
今は生殖能力の低下を感じさせる若者が増えて来たように感じています。
妊娠だけでなく、お産に関しても自力で産み落とせない妊婦もいて、すでに哺乳類として種の保存に黄色信号が灯る人もいるわけです。
そのような人でも食べ物を変えることによって、良いお産をすることが可能になったりする例をみていると、今のうちならまだ何とかなるような気がします。
むそう塾にも不妊で悩む方が次から次へといらっしゃいます。
多くの方は食事を改善して陽性寄りにしてあげると、ほどなく妊娠されます。
そして出産もスムーズです。
しかし中には奥さんの方は健康なのですが、ご主人の精子に問題がみられる場合があります。
それはてんこさんも書かれていることなのですが、こちらは一朝一夕に改善されないことが多いです。
冷えだけでなく、添加物の影響が考えられる場合もあります。
ご本人の問題ではなく、親からもらったものの中にその原因を見つけることもあり、無情を感じることがあります。
考えられることをすべて実行しても妊娠せず、諦めた頃にフッと妊娠する人がいたり、結婚して15年目に妊娠したり、結婚して10年間妊娠しなかったのに立て続けに3人も産んだりする人もいて、まさに神のいたずらを感じてしまいます。
妊娠と出産ほど神秘的なことはなく、それはまさに神の領域のように私は感じます。
子供をもうけることが当たり前という発想だと、不妊治療がどこまでも進みますが、それは得る(欲=陽)ことの極みであるようにも感じます。
そうではなく、与えられた環境の中で生きて行く(中庸)選択をするならば、まさに子供は「神様からの授かりもの」となりますね。
欲しいものは何でも手に入れる生き方をするのか、「足るを知る」生き方も選択肢に入れるかで、不妊の問題は大きく変わると思います。
どこかが満たされなかったとしても、どこかでその分が補われていることを当事者は気づかないことが多々あります。
そんなことにも想いを巡らせて不妊の問題を考えられたらいいなと思っています。

カテゴリー: マクロビオティックの指導現場からシリーズ
2件のコメント
マクロビオティックの指導現場より 妊娠・出産・母乳・離乳食の陰陽
これから妊娠・出産・授乳・離乳を経験するであろう女性たちだけでなく、ぜひ男性たちにも知っておいていただきたいお食事のことを書きます。
一般的なお食事は空腹を満たすためと、喜びや癒しのためにいただくことが多いのですが、マクロビオティックのお食事はその他にもう一つ目的があります。
それは「質の良い血液をつくる」ことです。
この一点のために陰陽を駆使してあれこれ模索するわけです。
しかしどんな場合でも忘れてならないのはバランスであって、何かを排除することではありません。
排除の論理は正しいマクロビオティックの考え方ではありません。
女性の体はとにかく冷やさないことです。
妊娠時期は特にその意識が重要で、体を冷やす食べ物や環境は羊水が増えるだけでなく、赤ちゃんに体脂がついてしまいます。
動物性脂肪が多い場合も赤ちゃんに体脂が増えます。
いつも少し陽性になる食事を心がけますが、あまり動物性が多いと子宮口が締まりすぎて、出産の時になかなか赤ちゃんが出て来れません。
反対に陰性な食べ物が多いと、出産の際に微弱陣痛で、こちらも赤ちゃんが出たり引っ込んだりすることになってしまいます。
妊娠中にしっかり陰陽バランスを取っておけば、痛みもほとんどなく、お産に要する時間も少なく、出血も最低限に抑えられます。
そしていよいよ授乳になっても、乳腺を詰まらせる要因が少ないので、スムーズな母乳ライフが楽しめます。
この母乳を飲ませることが、実はママにとっても大変重要なことで、妊娠で大きくなった子宮を収縮させたり、ホルモンを活性化させたりして、ママ自身がどんどん美しくなるのです。
よく、子供を一人産んだくらいの女性が最も美しくて色気があるというのは本当で、出産と授乳のご褒美でもあるわけです。
授乳中は乳腺を詰まらせる原因になるようなお食事は控えるようにして、母乳の質にいつも気を配りましょう。
さて、いよいよ離乳の時期がやって来ます。
断乳なんて寂しいことは言わないで、自然にバイバイできるようになりましょう。
だいたい母乳は生後1年くらいで乳糖の分解酵素がなくなって、澱粉の分解酵素がメインになりますので、歩けるようになったら離乳完成が照準です。
それ以後の母乳はスキンシップ目的のことが多いので、さっさと授乳を切り上げても構いません。
ただしこの離乳は個人差が大きいので、月齢に惑わされないようにしましょう。
一方離乳食ですが、育児本にとらわれずに、あくまで赤ちゃんの反応を優先して進めます。
赤ちゃんは自分にとって必要な食べ物とそうでない食べ物を本能で見分けますから。
最も注意すべきは、大人より薄めの味を心がけることです。
大人が味見してちょっと物足りないくらいでも良いのです。
なぜなら、赤ちゃんは大人より陽性だからですね。
食材や料理方法も陰性寄りで構いません。
大人の感覚で動物性のものをせっせと摂る必要はありません。
陽性が過ぎると大きく育ちませんので注意しましょう。
ああ、また時間がなくなってしまいました。
きょうは愛クラス(玄米の炊き方秘伝)があります。
ではこの辺で。

カテゴリー: マクロビオティックの指導現場からシリーズ
2件のコメント
マクロビオティックの陰陽を理解するための新しい試み

今日は「マクロ美風の陰陽落とし込み講座 各論特集」@京都を開催しました。
ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
今回は各論に入る前に色のお話をしました。
マクロビオティックの陰陽と色は大事な基本ですので、それにチャクラを絡めてしっかり身につけていただこうと思ったのでした。
今回は赤系統のお召し物を召された方々を拝見していて、それまでの経緯に思いを馳せていました。
それぞれに陰の状態の時期があって、今はご自分を取り巻く環境の変化が陽になっています。
それがお召し物の色となって反映していることに、一人納得していたのでした。
対応するチャクラがちゃんと開いていないとき、やはりその関係を表す着方をされていることが多いですね。
色選びを陰陽で見ると本当に面白いです。
写真左下のうつむいている赤いカーディガンの人は、本人の名誉のために書いておきますが、居眠りをしているわけではありません。
レジュメに目を落としていらっしゃるのです。
以前の彼女はかなり陰性で、とても赤いお色を着こなせないオーラが全開でした。
でも今はこんなふうに赤いお色を素敵に着こなせるようになりました。
中川さんから習ったお料理をせっせと復習して、中川さんに復習メールを送ってこられます。
まだまだこれから大化けしそうな感じなので、これからの更なる上達を楽しみにしているところです。
はっきりした色を着るには、一種の勇気のようなものがいります。
でも、それは最初の話で、一度その色を褒めていただくと次回からは好きな色の仲間入りをするようになります。
人間ってそんな単純とも思える動機で色に対するスタンスが変わるものなのです。
ということは、それで自分の陰陽も変化してくるということです。
そうしているうちに自分に自信がついて来て、目立つ色でも着こなせるパワーを持てるようになるのです。
私達の日常生活は常に衣服で身を包むわけですから、どんな色に身を委ねるかはとても大事なことなのです。
そんな背景があって、きょうの陰陽落とし込み講座の最初のテーマに選んだのでした。
まだまだお伝えしたいことが沢山ありますが、時間はあっという間に過ぎてしまうので、またブログを通じて、あるいはTwitterを通じて、日々陰陽を話せる場を作りたいなと思います。
外国語をマスターするのに最も良いのは、毎日その外国語がシャワーのように浴びられる環境に身を置くことですよね。
それならば、陰陽をマスターしようと思うなら、毎日陰陽を考える環境を整えることです。
毎日陰陽を話題に出来る環境に出入りすること。
それはマクロビオティックの本を読むことでも良いし、むそう塾のTwitter仲間と陰陽を話題にして頭を使うことでも良いのです。
そんなことをしているうちに、気がついたらすっかり陰陽頭になっていて、空気を吸って吐くうように陰陽を使いこなして行けます。
これからは私もTwitterで陰陽ワンポイントアドバイスを始めてみようと思いますので、実生活に則した陰陽をお楽しみください。
易しいテーマから陰陽に入れるようにしますので、お気軽にご参加くださいね。
カテゴリー: マクロビオティックの指導現場からシリーズ
33件のコメント
花びらのようにやわらかにマクロビオティックを取り入れましょう

ただ今変身の練習中。
どうですか?
少しは変わったでしょう?
すっぴんの健康な山形美人さんです。
これからどんどん女度をアップしますのでお見逃しなく!
マクロビオティックで中から健康を!
美味しいお料理で真の幸せを!
それを可能にするのがマクロビオティックの陰陽理論です。
この花びら生姜のように艶っぽくなってね。

(花びら生姜 料理:中川善博)
カテゴリー: マクロビオティックの指導現場からシリーズ
20件のコメント
京料理人だからこそ語れるマクロビオティックの裏側
中川さんがいつも思っていることを伝えたいと、珍しく長い文章を書いてくださいました。
いつもお料理ばかり作っていて、なかなかこのようなお話をする機会がないものですから、公開授業として記事にさせていただきます。
むそう塾に学んでくださっている方は勿論のこと、まだ一度もお会いしたことのないあなたも、何年もマクロビオティックをされている方も、そして、マクロビオティックが初めてという方も、みんなで「家庭のお食事」を考えてみましょう。
皆さんの様々なご感想をコメント欄に残していただけたら嬉しいです。
<以下文章:中川善博>
【味付けの指向性の話】
指向性というと音や光などに使われる言葉でありますが、私は料理を考えるときに「味付けの指向性」という使い方をしています。
どういう意味かお話します。
いま、あなたが作っているお料理は誰が食べるのでしょう?
おそらくはご主人、お子様といった「家族」という社会構成の最小単位に属する人たちに食べさせるために作っているのではないでしょうか?
それに対して街へ出かけてレストランや料理屋に入ってメニューを見て注文した料理はどうでしょう?
その店のキッチンにいる人と昔から懇意にしている場合をのぞいて殆どの場合、誰が作っているか、または誰が食べるのかは判らない、ということになります。
その料理を食べてもらう対象は「お客様全員」となります。
何名、何百名、何千名かもわかりません。
商売用の味付けは昔から「10人のうち6人が美味しいと言えば繁盛する」といわれており、それほど全員に喜んでもらえる味付けは難しいのです。
この6/10の味付けを指向性の低い味付けと呼んでいます。
もっと指向性の低い味付けがあります。
なにかわかりますか?
それは低価格戦略をとっている外食産業です。
堂々と特別に美味しくなくても構わないという意味で、「不味くなければ良い 安ければ」という戦略をとっている会社がありました。
私には違和感アリアリでどうしても納得できなかったのを覚えています。
「費用対効果」便利な魔法の言葉です。
【料理と調理】
味付けの指向性のお話と通じる事でもあります料理と調理の違いについてもお話しておきましょう。
大雑把ですが、不特定多数の方へ提供するものは調理、誰が食べるのか判っているものは料理、と私は使い分けています。
「調理」は、コンビニエンスストアに並ぶたくさんのお弁当、ファミリーレストランのメニュー、社員食堂の献立、学校給食などなど。
食べる人の顔が見えない判らない状態で作るので、無難で大ハズレがないように作られています。
「料理」は、この味をこの人に食べてもらいたい、このお客様は関西出身だからすこし色目を薄く仕上げて、最近子供がクラブでレギュラーになって運動量が増えたのでタンパク量を増やそう、主人は昨日飲み会だったので消化の良い陽性なものを少量で、という風に、食べる人の顔が見えている、判っている場合に使うべきだと思っています。
ですから調理師と料理人では自ずと仕事が違うのです。
もちろんどちらが上とか下とかはありません。
【陰陽料理(マクロビオティック料理)と和食】
私達は日本に住んでいて、日本人である桜沢氏が提唱したこともあり、マクロビオティックというと玄米菜食を厳しく実行することのように誤解しがちです。
しかしそれは大きな間違いで、マクロビオティックというのは生き方の事であるのです。
生きるためには「食う」ことが必須であるために、マクロビオティック実践者のための料理が重んじて語られてしまうのです。
そしていつの日かマクロビオティックという大いなる偏食が全てであるかのように、前に出てきてしまったのです。
玄米菜食が世界で一番素晴らしいのであれば、世界中で玄米菜食をすればいいのか? そんなことはありませんよね?
地球上には米が出来ない地域もありますし、野菜が育たない土地もあります。
そこに住んでいる人はマクロビオティックは実践できないのか? 変な話です。
西洋人がヨーロッパで玄米を炊いて漬物を食べて味噌汁を飲んで、それを何代も何代も続けるのでしょうか?
そうではありません。
ヨーロッパにはヨーロッパで何百年と食べ続けられてきた伝統料理があります。
その土地がもたらしてくれる作物をその土地の陰陽とその土地に住む人間の体調を考えながら料理をする。
これがマクロビオティック料理です。
むそう塾では、食べてくれる人が陰陽バランスを取りやすく、中庸からやや優しい陽性に生きていける料理をお教えしています。
これを陰陽料理と呼んでいます。
中川善博が和食の料理人出身でありますゆえに、京料理やおばんざいからの献立をお教えしていますが、陰陽料理は決して和食だけで作るものではありません。
赤道直下の国には赤道直下の環境に則した陰陽バランスがあります。
野菜も穫れないような北限南限にも、北限南限なりの陰陽バランスがあります。
日本の玄米をアラスカに持って行って梅干しで食べるのが陰陽料理ではありません。
そこを誤解しないようにしましょう。
女性が家庭を守って男性が外に働きに出て給料を持ち帰り、家族を養う。
今となっては「サザエさんのはなし?」なんて笑われるほど夫婦共働きが当たり前になりました。
共働きが当たり前になったとはいえ、ご主人が家事も共働きしてくれているご家庭はまだまだ少ないのではないでしょうか?
同じように外で働いてきた奥さんが家族の食事を準備します。
手間のかかる料理などできるわけもなく、簡単に数品を作り、あとは帰宅途中にデパ地下などで買い求めた「中食」と呼ばれる調理済みのおかずです。
それを皿や鉢に移して(へたをするとパックのまま)食卓に並べます。
タイマーで炊きあがったIH炊飯器には陰性な白米があり、保存料がたっぷり入ったパック入りの漬物には乳酸菌など在るはずもなく、あればいいというレベルで大事な食卓を満たすのです。
中食やインスタントや保存料の入ったおかずは主婦の忙しさ、時間の無さを補います。 それは言い換えれば時間を創りだしているのです。
しかしどうでしょう。
苦労して時間を創ったつもりなのに、この食べる人の事を考えていない調理品を何年もの間食べていてずっと健康でいられるのでしょうか?
遅かれ早かれこの家族は病院や薬の世話になっていくでしょう。
そうして、創ったはずの時間がブツッ!と切れてなくなっていることに気づくのです。
世の中にマクロビオティックスクール、マクロビオティッククッキング、などがたくさんあり、前述した不健康な食生活を悔い(喰い)改めようと、多くの女性達が毎日のように学びに通っておられます。
そこで習うのは手作りの良さ、添加物、動物性食材や乳製品の禁忌。
私の眼にはどんな体質、体調の人にも同じような一辺倒な調理法を教えているように見えてしまいます。
何%かの人にはドンピシャでマッチするので、奇跡のように体調が良くなって感謝のはがきがこんなに届きました!状態になるでしょう。
そしてそのスクールはそのはがきだけをアピールして宣伝します。
またそれを見て体調の悪い人が引き寄せられる。
必要以上に陰性に振られた体調はどんどん正氣をなくし、女性は貧血になり生理が止まり、生干しのミイラのようになります。
毎月毎月愛クラスにはそんな生干しさんが来られます。
そして美風さんのメールボックスは、まるで駆け込み寺のように生干しメールが積み上げられていきます。
そんな無責任な指導をしてるから、トンデモ理論とか、なんちゃってダイエットとか非難を浴びるのです。
桜沢氏も大森氏もそんな指導は決してしていなかったはずです。
ちゃんと1人1人と向き合って、その人オリジナルの指導をし、その結果を鑑みてさらなるフォローを重ねる。
ここまでやって初めてマクロビオティックな指導といえるのではないでしょうか。
そんな今夜もどこかで、塩を減らして肉を抜いて甘いものは止められない生干しミイラが誕生しているのです。
(むそう塾 塾長)

(寒桜 宝泉 京都駅店)
カテゴリー: マクロビオティックの指導現場からシリーズ
87件のコメント