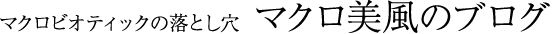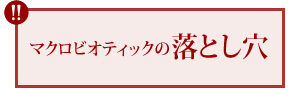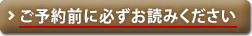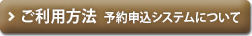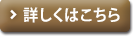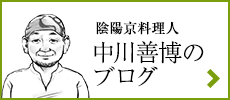ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- これから開催予定の講座案内(2026.1.22現在)
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)
- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ
- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?
- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内
- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ
- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在
- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内
- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)
- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」
- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著
- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能
- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内
- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて
- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!
- ポリファーマシー(多剤服用)の心配
- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと
- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた
- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから
- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん
- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます
- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内
- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内
- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内
- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内
- 「2026年度(第6期)自由人(びと)コース2」受付開始のご案内
最近のコメント
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より
カレンダー
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
カテゴリー
- 講座のご案内・連絡事項 (1,223)
- 健康情報 (2)
- 新しいむそう塾 2022年 (28)
- 料理は呼吸と同じ (24)
- うれしかったこと (198)
- 玄米の炊き方講座 (216)
- お弁当の想い出 (6)
- 京料理人 中川善博の動画 (83)
- 京都やマクロビオティックのことなど (208)
- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)
- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)
- むそう塾スタイル (51)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)
- 食べたもののようになる (107)
- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)
- 中川式糠漬け (269)
- 中川式出汁巻き玉子 (24)
- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)
- 幸せコース感想文 (36)
- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)
- 子育て・野口整体・アトピー (308)
- 男子厨房に立つ (17)
- 新型コロナウイルス (133)
- からだ (561)
- こころ・想い (533)
- 食べ物あれこれ (338)
- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)
- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)
- 陰陽ひとり立ち講座 (93)
- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)
- 体験談 (134)
- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)
- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)
- マクロビオティックと歯科治療 (24)
- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)
- 本の紹介 (121)
- その他 (208)
- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)
- マクロビオティックわの会 (9)
- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)
- むそう塾 パスポート発表 (204)
- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)
- ワーママさんの応援 (4)
- 中川善博の入院日記 (12)
- HP記事更新のお知らせ (9)
- 夫の病気関連 (9)
macro88のtweet
-
「マクロビオティック京料理教室 むそう塾」カテゴリーアーカイブ
出汁巻き玉子を得意料理にするための鍵は無重力感とお箸の持ち方です
昨日は「中川式出汁巻き玉子特訓講座」を開催しました。
すでに幸せコースで習った人と、1期生で習っていなかった人のミックスでしたが、色々な場面での一コマ一コマが脳裏に焼きついています。
まさに笑いあり涙ありの一日でしたが、それぞれの皆さんの頑張りが熱く伝わって来て、とても氣の良い空間でした。
出汁も玉子も途中で追加するほどの量を巻き進み、最多数はHoさんの16本でした。
涙のNoさんは12本という具合に、自宅で一人なら絶対にイヤになってしまい、上達には限界があるところを、即座に中川さんの修正が入るため、知らず知らずに上達して行くのでした。
消費した玉子はなんと273個です!
この講座で感じたことは、続けて練習することの効果、的を得た指導、同じことをする仲間の存在、そして何よりiPhone5sのスローモーション機能の大活躍でした。
自分の腕の動きを知ることによって、一気に仕上がりに変化が出てきました。
スポーツの練習でも使われている手法ですが、これは効果がありますね。
iPhone5sじゃなかった人は、この動画が残せず残念でした。
次の写真の人達に共通の「あること」があります。
それはお箸の持ち方が中川式でちゃんと持てていることです。
特にすぐ下↓のNoさんは、左利きを右手持ちに直しての特訓でした。
右手で桂剥きも出来ます。
なんという努力家でしょうか!
ですから、達成感も人一倍強かったと思います。
フライパンからふっくらとはみ出た玉子の膨らみが、上手に巻けたことを物語っています。

Hoさんもきちんと中川式のお箸の持ち方ができているので、このように綺麗に玉子を立てられるようになりました。
課題は精神面での焦りをなくすことです。

Naさんもご覧のとおり、ちゃんとお箸を持っています。
この腕の角度を忘れずにすれば色気のある巻き上がりになります。
中川さんの動画の手つきには色気がありますものね。

オマケ
手に汗する場面がありましたが、確実に上達しました。
必ず出汁巻き美人になりましょう。
すでに美人ですが。
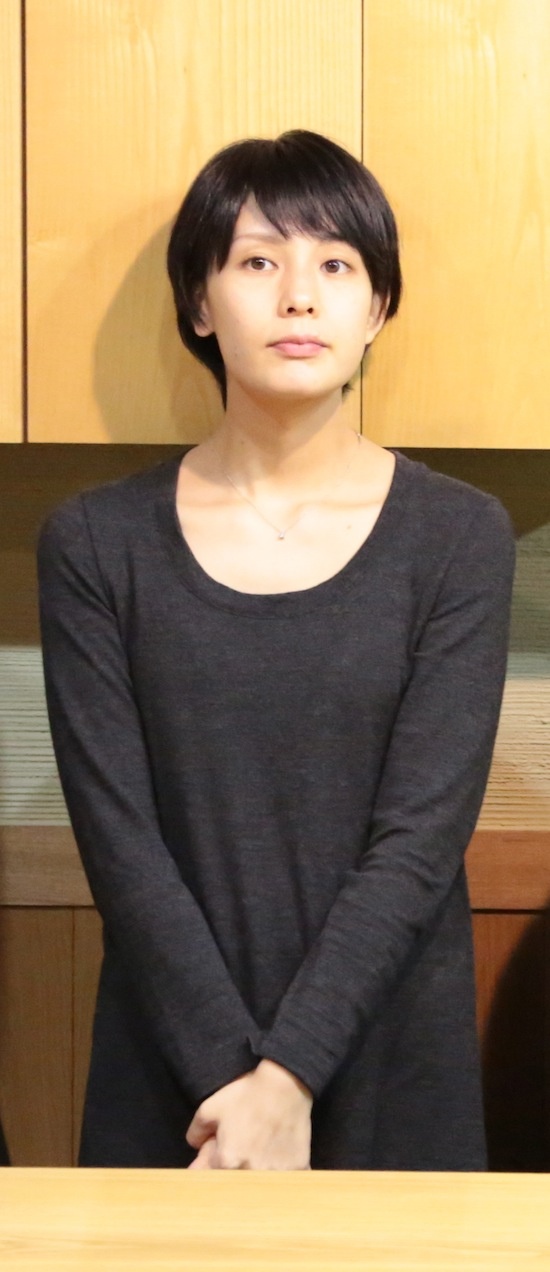
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾
8件のコメント
柚子味噌の美味しさや玉ねぎの甘さに癒やしを感じる福ZEN

(写真は講座のための特別メニューなのでおかずを少なくしてあります)
きょうから3日間はむそう塾の単発講座で福ZENがいただける。
そろそろ写真のように柚子味噌が美味しい季節。
3日間どんな福ZENが登場するのかな?
3日連続受講される塾生さんもいらっしゃるので、微妙に福ZENの内容も変わることは想定内。
ワクワク♪
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾
2件のコメント
グルメも唸るマクロビオティック料理が中川善博の陰陽料理
人はなぜ美味しいものを食べたがるのでしょう?
それは美味しいものを食べた時の満足感が心地良いからですね。
ですからお料理には「美味しい」ことが絶対条件です。
「体のために良い」という観念的なお食事では満足できません。
ですから病人であっても、いや病人だからこそ美味しいことが不可欠なのです。
誰だって具合の悪い時には食欲が落ちるからです。
そこを助けるのは美味しさにほかなりません。
では、グルメ料理なら病人は元気になれるのでしょうか?
巷で美味しいと評判のお料理なら病気は良くなって行くのでしょうか?
それなら嬉しいのですが、反対にグルメ料理ばかりでは健康を損ねてしまう人も多いですね。
美食家に病人が多いのはそのためです。
そこにマクロビオティック料理の存在意義があるわけで、じわじわとマクロビオティックの知名度も上がってきましたが、それとともに誤解されていることがとても多くて、困った現象だなあと常々思っています。
結論からいうと、グルメ料理とマクロビオティック料理の違いは、陰陽バランスがあるかどうかということです。
口に美味しく感じる面だけ強調するとグルメ料理になりますが、人間の身体と健康を考え抜いて陰陽を用いて作ればマクロビオティック料理になります。
それなら、マクロビオティック料理でありながらグルメの要素を兼ね備えれば文句なしですね。
それがむそう塾でお伝えしている「中川善博の陰陽料理」です。
一般的に広まっている不味いマクロビオティック料理ではなく、グルメも唸るマクロビオティック料理です。
なお、一般的には動物性や白砂糖や乳製品を使わないのがマクロビオティック料理だと思っている人がとても多いのですが、肝心なのはいつも陰陽バランスを保っているかどうかです。
すでに罹ってしまった病気を改善することを目的としたマクロビオティック料理(食養料理)と、病気にならないために健康をキープしようとするマクロビオティック料理は、きちんと分けて考える必要があります。
そうでないといたずらに窮屈でかえって体調不良を招く結果になってしまいます。
むそう塾にはここを混同している人が次々と来られます。
マクロビオティックの広め方にも問題があるのですが、マクロビオティックを知ってから体調を崩した人を見ると本当に可哀想になってしまいます。
マクロビオティックを誤って実践すると、「著しい偏食」をしているだけになるのです。
これはかなり危険です。
私は長い間このような人を見てきましたから、何としてもこの危険なパターンに落ち込んでほしくないと思っています。
そのために一般の相談も受けながら、一人でも多くの人に正しくマクロビオティックが伝わるよう、文字どおり日夜奮闘しています。
もっと伸びやかに、もっと大らかに、たまにはこんなパスタや、こんなお鍋を楽しんでください。
ほっこりと幸せになれるひととき。
それが良い陰性です。

(鳥なんば 京都 尾張屋 高島屋店)
※ 葱多めと注文して陰陽バランスを図ること
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾, 料理人 中川善博の陰陽料理, 食べ物あれこれ
6件のコメント
プロの料理人による栗の皮のむき方を動画で公開しました
音楽あり、赤ちゃんの泣き声ありの動画ですが、プロの料理人が栗の皮をむくところを公開しました。
まるで桃でもむくかのように、するするとむいてしまう手つきは凄いです。
中川さんのむく栗は艶っぽくて、萬亀楼さんでの修業時代でも店主から「色っぽいわあ!」と言われたそうです。

(むいた人:中川善博)
動画の最初の方では栗の皮を切るところが入っていませんので、こちらで補っておきます。


ここから先は動画をごらんください。
1個目と2個目では栗の形が違うことに注意。
包丁を入れる順序が違います。
[youtube]
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾
コメントする
マクロビオティックの「食べたもののようになる」は本当です
今年も幸せコースの食事日記を拝見する受業が終わりました。
これは1か月間受講生に食事日記をつけてもらって、その結果に対してマクロ美風からアドバイスをするものです。
食事日記は決められた項目ごとに分けて記入するのですが、その項目はずっと変わっていません。
それほどそれらの項目は重要であり、心身への影響が大きいからです。
今回3クラスの食事日記で感じたことをまとめてお伝えしますので、それぞれの方がご自分のことと思って受け止めてほしいです。
(1)<記入方法>
第三者が読むことを前提に「読みやすさ」を心がけて記入されている人とそうでない人の差が大きかったです。
このことは「伝え方」としての陰陽を表しますので、これも陰陽判断しています。
・整理されていて見やすい=陽性
・要点がなく記入も怠りがち=陰性
(2)<主食の量>
残念ながら主食の量がほとんどの人で理想的割合を満たしていませんでした。
これだけ玄米ご飯に力を入れているむそう塾ですらこの有り様ですから、一般家庭ならどのようになっているかを想像すると、それは病気になるだろうなぁと思いました。
最低でもおかずの2倍はご飯を召し上がってください。
それを簡単に実行出来るように「ご飯2口おかず1口」とおまじないのようにお教えしているのですから。
(3)<主食の種類:白米>
むそう塾生でありながらほとんど白米を召し上がっている人がいました。
申し訳なさそうに玄米ご飯が登場する日がありましたが、それはまず玄米ご飯の炊き方がパスポートレベル未満になっていることが予想されます。
ご家族のご希望を聞いて白米という人もいましたが、それなら炊き分けをするべきですね。
白米を召し上がっていて体調が悪いなんておかしいと気づいてほしいです。
それだったら玄米ご飯に変えて少しでも体調の向上を目指すことは1か月間でも可能です。
そして、たった1か月間でも玄米ご飯はその効力を見せつけてくれます。
(4)<主食の種類:パン>
忙しいからとの理由でパンに逃げている人がいました。
でも、本当にご飯を炊く時間がないほど忙しいのでしょうか?
私はむしろご飯を炊いて体力をつけて仕事をササッとこなして、お料理を癒やしと気分転換として生活のリズムに組み込んだら良いと思います。
これができればプラスの循環に、出来なければマイナスの悪循環に陥ってしまいます。
一念発起してこの循環を良い方向に回してください。
なお、パンが好きな人はストレスいっぱいの人が多いです。
こんな人はせめてパンではなく、麺類に逃げてください。
できればお汁のある麺類に。
(5)<主食の波動と格>
玄米であっても白米であってもプレーンで召し上がるのが最も波動が高く、混ぜ物をするとその分だけ波動が落ちていくことになります。
異質のエネルギーが入るので波動が乱れるのです。
ですから、混ぜご飯は毎日ほしくありませんね。
体は無意識に知っているのです。「飽きる」という状態で。
また玄米に雑穀を混ぜることは主食の格を落とします。
主食はピュアな状態で取り込むことが最も精神性を高めます。
(6)<副食の量>
皆さんに共通していること。
それはおかずが多いことでした。
おかずが楽しみなんですね〜。
でも、どんなに好きなおかずでも上記の割合を守ってください。
「一汁一菜」は貧しいことではなく、究極の健康食であることを忘れずに。
好きなおかずをお腹いっぱい食べて、それでも元気に長生きしている人もいますが、その数は圧倒的に少ないです。
ストレスのはけ口を食事に求めてしまうと、おかず食いになってしまいます。
(7)<発酵食品>
これが80%満たされていませんでしたね。
そもそも発酵食品を知らなさ過ぎます(泣)
発酵食品は自分でも作れますから、ぜひ毎日少量で良いですから摂ってください。
毎日摂ることがポイントです。
腸の働きがグンと良くなります。
そういえば糠床を死守しておられるご家庭で、ご主人の腸が快適なのでご主人が糠床ハウス(勿論家の中に)を作ってくれたという話を聞きました。
微笑ましいですね。
(8)<水分の種類>
お味噌汁やお吸い物は主食がご飯物なら毎回ある方が好ましいです。
たとえば温かいおうどんを召し上がった時に、汁を全部飲み干すことはしなくても、ホッとすることを実感されていませんか?
あれは水分が人間には必要で、それが入ると体がホッとする好例です。
これらの水分が不足していると、お茶やコーヒーを飲みたくなります。
しかしこれらは利尿作用があるので、そんな時には真水を飲む方がよいです。
水分の摂り方は塩分があるかどうかも重要なポイントです。
なお水分には体に吸収されるものと素通りするものがあることをお忘れなく。
* * *
以上ザックリと食事日記に対する感想をまとめてみました。
今回も私が手応えとして感じたこと。
それはやはり「人は食べたもののようになる」ということでした。
目の前の人をパッと見ただけでその人の食べているものが判ってしまうのがマクロビオティックの凄いところなのですが、今回も3クラス分の食事日記を拝見して見事にそれを感じています。
ますます自分の眼に自信を持ちました(笑)
身体は食べているものを隠せませんね。
内面の精神性まですべて丸わかりです。
ああ、あの人のちゃらんぽらんさはこのおかずが原因ねとか、こんなものばかり食べているから体力がつかないのよとか、これが少ない(多い)から太れないのよ(痩せないのよ)とか、はたまた、この器が原因ねとか、その考え方では何を食べてもダメねとか、ポイントは多岐にわたります。
そのポイントはすべて陰陽で判断できるのですから陰陽って万能です。
そしてマクロビオティックでよく言われる「食べたもののようになる」という言葉は、私の中で日々確信の更新をし続けています。
精神面への影響も含めて食べ物の影響は強烈です。
「You are what you eat.」
(あなたはあなたが何を食べているかで決まる)
この格言に嘘はありません。

(蓮根ボール マクロビオティック料理教室 むそう塾)
カテゴリー: マクロビオティック京料理教室 むそう塾
10件のコメント