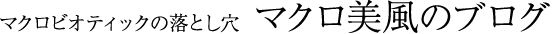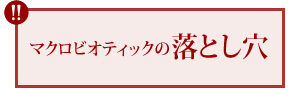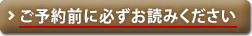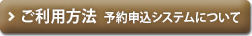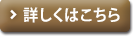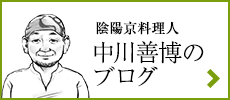9月15日に、日本CI協会の主催で開催された、久司道夫先生の講演会について、私の考えがまとまりましたので、ご報告します。
結論から申し上げると、講演会の細かい内容や私の個人的な感想については、書かないことにしました。
それは、次のような理由によります。
* * * *
すべての物事に対する判断は、自分の目と耳を使って、自分の責任においてするものだと思います。
マクロビオティックにおけるところの、「最高判断力」を身につけるためにも、各人がそれぞれの視点から考えるのが原則だと思いました。
* * * *
先の私の記事に対して、多くの方からメールをいただきました。
特に最近は、ミクシィを通じてのメッセージが、とても多くなりました。
ブログのコメントより、公開性がない分、本当の気持ちを書きやすいからでしょうね。
沢山のご意見を寄せてくださって、本当に感謝しております。
99%のご意見が、「感じたことをありのままに書いた方がよい」というものでした。
しかし、結果は、そのご期待に沿うことができず、心苦しく思っております。
ごめんなさいね。
* * * *
今回、私は、次のようなことを考えました。
◆情報って何だろう?
◆本当に必要な情報って何だろう?
◆私は何のために、ブログを始めたのだろう?
◆私は、マクロビオティックに対して、何を求めているのだろう?
お寄せいただいた沢山の文章の中に、次のような一文がありました。
「喜びは分かち合う必要がありますが、 批判というのは分かちあう必要のある情報でしょうか? 」
この文章を拝見して、私は、自分の未熟さを思い知りました。
涙が止まりませんでした。
嬉しかったです。
ブログを通じて知り合い、ミクシィを通じて本心を語り合い、遠く離れていても、「マクロビオティックの種を播こう! 」という共通目的のもとに交流がつづき、素晴らしいご意見を頂戴できたことが、本当に嬉しかったです。
* * * *
もう一度、
「喜びは分かち合う必要がありますが、 批判というのは分かちあう必要のある情報でしょうか? 」
この言葉をいつも胸に抱いて、気持ちのいい文章を書いていきたいなぁと思っています。