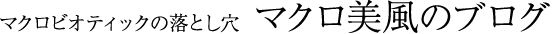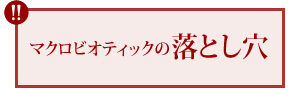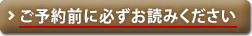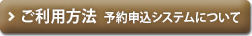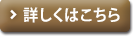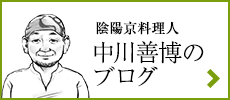次のようなお悩みのメールが届きました。
ご主人は欧米人、奥様は日本人でアメリカにお住まいです。
マクロビオティックのお勉強もされているのですが、壁にぶつかってしまいました。
体に合わないマクロビオティックをされて体調不良の方も多いことでしょうから、ご一緒に考えてみましょう。
<Bさんからのメール>(抜粋)
正直、なにをどうしていいのか、まったくわかりません
ごはんのことでは何度も壁にぶち当たっています。
大好きな料理のはずなのに、こんなにごはん作りが苦痛だと思ったことはない、とまで思う時もありました。
何をどう作っていいのかわからないのと、ただでさえ少なくなった自分の時間が料理で終わってしまうのがつらく感じたことも理由です。(今は娘と遊びながらでも、少しずつ料理をしていけるようになって来ましたが)
その度にいろいろ考えたり、思い直したりして、なんとか今日まで来ていますが、とても美風さんのように心を込めて、一度一度の食事を大切に、とは出来ていない、と思います。
娘はよく食べる子で、食べだすとかなりの量を食べます。
お腹もパンパンです。
母乳が終わったあとはそうなる、と聴いていたので、そんなものなのかなぁ、と思っているのですが母乳をやめてからすでに5ヶ月になろうとしています。
好きなものは、うどん、豆腐、パスタ、きのこ類、海藻類,豆類、これらはあればあるだけ食べると思います。おそらく、漬け物、梅干し、味噌なども。そして、みそ汁(かなり薄味で、毎食2杯くらい子ども用のお椀に飲みます)などのスープもかなり飲みます。
パン(週に1、2度くらい、大好きです)、大根、人参、かぼちゃ、テンペ、セイタンなども食べます。レモンは皮までかじります。
トマトも好きだけど(かなり食べます)、今は食べさせていないです。
時々、青菜の茎も喜んで食べます。
魚も週に1度くらいは食べるし、これまでに卵と鶏肉,豚肉も食べたけれども、好きみたいです。
ごはんもおむすび食べる!と好んで食べたり、おかわりをする時もあります。
進んで食べたがらないのは、朝が多いです。
まず起きると遊んで、そして、私たちが食べているのを見て、自分も!となります。
夜食べ過ぎているのでしょうか。でも、食べる子なので、食べだすと夜でも朝でも(進んで食べなくても、そうなります)昼でも、もうこの辺で、と量でコントロールするのが難しくなります。
何か出された食事がもの足りないから、量で満たそうとしているのでしょうか?
基本的におやつはあまり食べていません。
本人が食事以外の時間に、お結び、と言うので食べさせるか、たまにリンゴ(これも大好き,きっと出せば毎日でも食べると思います)くらいです。
おやつをあげなくても、特に夕飯まで問題ないこともあるので、必要ないかな、と思いあげていないのですが。
それとも、おやつがないから、夕飯にたくさん食べて、それが朝までひびくのでしょうか?
お腹がすかないなら食べなくてもいい、と私も思うのですが、そうなると、私たちと違う時間帯の食事になってしまうし、とまた考えてしまいます。
お腹空いていなくても、パンやうどんは食べたがるので、それで釣ってしまったりも・・・。
味付けも塩味はほとんどいらない、と思って、かなり薄味です。
それでも、蒸したり、茹でたりしただけの野菜も、好んで食べるのです。
朝はごはんとお味噌汁と納豆,たまに漬け物
昼は麺類や粉もの
夜はごはんとお野菜や豆,豆腐などと汁物
というかたちの食事です。
本当は愉しく美味しくみんなで食卓を囲みたいのに、時々とってもつらいです。
できることなら、マクロビの考え方からいっさい離れて、ごはんを作り食べたい。
でも、そんなことはもう出来ません・・・。
もし、そう出来たとしても、他の何か、で結局は自分を追い込むような気がします・・・。
また、私自身も、今食べておかなければ食べられない、という気持ちでごはんを食べることがよくあり、そのストレスが解放される娘が寝ている時や夜に、スナック菓子などを食べてしまいます。
昨日,今日と玄米ご飯を多めに食べて、ぐっとこらえてスナックは食べずにいられました。
こうして、自分を正して行くしかないのですよね。
妊娠するまでと妊娠中はあんなに厳格な玄米菜食が出来ていたのに、その反動でしょうか?
カリカリしたものがとても食べたくなり、またパンなども食べてしまうのです。
スナック菓子は、一度に一袋簡単に食べてしまいます。あればあるだけ食べようとしてしまいます。
私のごはんも陰陽バランスが取れていないのだろうなぁ、と思います。
娘が食べ物に執着しているように思うのですが、それはまさに、私自身の姿を見ているようにも思えます^^;
こんなにまとまりのない、長文でごめんなさい
ずっと誰かに聴いてほしくて仕方なかったことを,書かせていただきました。
読んでくださってありがとうございます
<マクロ美風より>
こんにちは。
あのね、Bさんはマクロビオティック病に陥っていますよ。
そしてストレスだらけです。
あなたもお子さんも、間違ったマクロビオティックの被害者ですね。
マクロビオティックを始めてしばらくは体調が良くなりましたが、時の経過と共に体調に合わないマクロビオティックになっていますね。
あなたのような人をいーーーっぱい見ているので、可哀想なくらいです。
結論として、お子さんもあなたもお食事から満足感を得られていないのです。
だから量で満足するまで食べようとしたり、お菓子で満たそうとしたりするのです。
つまり、お食事からエネルギーをもらえていないのですね。
頭でマクロビオティックをしている人の典型例です。
ご主人とお子さんとあなたの中に、動物性の蓄積はどれだけあるか?
そのことを考えれば自ずと答えが出ます。
そのことをしっかり考えてマクロビオティックをしないと、大きな間違いをすることになりますよ。
もしご主人の体調が良いのなら、あなたとお子さんは塩分を今までより多く摂ってごらんなさい。
あるいは動物性を少し摂ってごらんなさい。
実験的でも良いから。
必ず変化がありますから、反応をよく確認してみてください。
もしそれが出来ないのなら、あなたの考えているマクロビオティックから距離を置いたほうが無難でしょう。
本来のマクロビオティックの良い点を取り入れられなくて、マイナス面だけに振り回されているからです。
あなたと同じような状況から普通食に戻して、体調も精神面も安定したむそう塾生が何人もいますよ。
少量の動物性を取ることは「マクロビオティックを捨てることではなくて、本来のマクロビオティックのあり方に合わせる」ことなのです。
きっとあなたはこの部分が理解不能なのだと思います。
マクロビオティックの核心部分の理解を間違っているからです。
私のブログで何回も発信している一連の記事を上滑りで読んでいませんか?
あるいはあなたがお気に入りのサイト自体に誤りがありませんか?
対処療法的にマニュアルとしてマクロビオティックをとらえないで、「普遍の理論」として理解できていますか?
ここが一番の問題です。
あなたもお子さんも、そしてご主人もマクロビオティックの被害者にならないように、心からお願いします。



ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- 「おうちレストラン 第3弾」のご案内と受付開始!
- これから開催予定の講座案内(2026.1.24現在)
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在)
- 「中川式ハンドドリップ珈琲実習講座」開催のお知らせ
- 梅が咲いた 政治が動く 陰陽はいかに?
- 「春休み キッズクラス」受付開始のご案内
- 「春休み キッズクラス」日程のお知らせ
- 「スポット受講」ご希望者一覧 2026年1月13日現在
- 「おせちの盛付秘伝講座」受付開始のご案内
- 「おせちの盛付秘伝講座」受講ご希望者のお伺い 1/11現在
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった!
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在)
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾)
- 「心に響く小さな5つの物語」「縁を生かす」
- 「医者が教える世界一やさしい薬のやめ方」崎谷博征著
- アックスヤマザキ「子ども向けミシン」の記事に泣けた朝
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能
- 「中川式アジア料理講座 第1弾」受付開始のご案内
- 「2025年度秘伝コース」のおせち授業を終えて
- 脳梗塞後でもネクタイが結べるようになった!
- ポリファーマシー(多剤服用)の心配
- 京都 祇園石段下「いづ重」で感じたこと
- 味覚障害の夫でもご飯の味がわかるように炊き方を変えてみた
- 「中川式小豆絹玄米ごはん」の美味しさを塾生さんのコメントから
- 「冬休み キッズクラス」をプレゼントしたお母さん
- 2026年度のコース受付にあたって感謝を申し上げます
- 「2026年度(第1期)自由人(びと)コース7」受付開始のご案内
- 「2026年度(第2期)自由人(びと)コース6」受付開始のご案内
- 「2026年度(第3期)自由人(びと)コース4」受付開始のご案内
- 「2026年度(第4期)自由人(びと)コース3」申込開始のご案内
最近のコメント
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に マクロ美風 より
- むそう塾塾長のぜいたくな「茶蕎麦」が最高だった! に Namika より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に マクロ美風 より
- 2025年度おせち投稿一覧(マクロビオティック京料理教室むそう塾) に つむぎ より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に マクロ美風 より
- ほどよい陰性が心地よい 生きるうえでヒントになる才能 に めぐ より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に マクロ美風 より
- マクロビオティックの陰陽を改めて 驚きのビーフシチュー に おはる より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に マクロ美風 より
- 2026年度各コースの受講ご希望者状況(2026.1.4現在) に 佐藤美奈 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に マクロ美風 より
- 人は人に元気をもらうんだなぁと実感 夫のケース に てんこ より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に おはる より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に マクロ美風 より
- 夫がディサービスを希望 新宿Bicerin(ビチェリン)で休憩 に かのん より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に メロン より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に マクロ美風 より
- 「マクロ美風の陰陽五行説講座」第2期を終えて に おはる より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に マクロ美風 より
- 「瞬速料理5品 夏バージョン」の開催について に おはる より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に マクロ美風 より
- 再開催ご希望講座一覧(2026.1.22現在) に ここ より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に マクロ美風 より
- 私を支えて栄養補給してくれる仲間たち に NANA より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に マクロ美風 より
- 介護生活の現実は両者の精神面の理解が大切だと実感 に NANA より
カレンダー
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
カテゴリー
- 講座のご案内・連絡事項 (1,224)
- 健康情報 (2)
- 新しいむそう塾 2022年 (28)
- 料理は呼吸と同じ (24)
- うれしかったこと (198)
- 玄米の炊き方講座 (216)
- お弁当の想い出 (6)
- 京料理人 中川善博の動画 (83)
- 京都やマクロビオティックのことなど (208)
- 塾生さんのメールから心に響いたこと (82)
- マクロビオティックの指導現場からシリーズ (431)
- むそう塾スタイル (51)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 (1,198)
- 食べたもののようになる (107)
- 料理人 中川善博の陰陽料理 (176)
- 中川式糠漬け (269)
- 中川式出汁巻き玉子 (24)
- 中川式鉄火味噌の体験談 (25)
- 幸せコース感想文 (36)
- マクロビオティックが楽しい♪ (3,575)
- 子育て・野口整体・アトピー (308)
- 男子厨房に立つ (17)
- 新型コロナウイルス (133)
- からだ (561)
- こころ・想い (533)
- 食べ物あれこれ (338)
- マクロ美風の陰陽落としこみ講座 (17)
- マクロ美風の家事アドバイス講座 (379)
- 陰陽ひとり立ち講座 (93)
- マクロビオティックの陰陽で考えてみよう (114)
- 体験談 (134)
- むそう塾の雰囲気(塾生の体験談を含む) (70)
- マクロ美風の体験的マクロビオティック (78)
- マクロビオティックと歯科治療 (24)
- 桜沢如一先生の陰と陽 (9)
- 本の紹介 (121)
- その他 (208)
- 「おしゃべり陰陽cafe 」 (11)
- マクロビオティックわの会 (9)
- 大森英櫻・磯貝昌寛 (8)
- むそう塾 パスポート発表 (204)
- プロが個人指導するマクロビオティック陰陽弁当 #musobento (90)
- ワーママさんの応援 (4)
- 中川善博の入院日記 (12)
- HP記事更新のお知らせ (9)
- 夫の病気関連 (9)
macro88のtweet
-