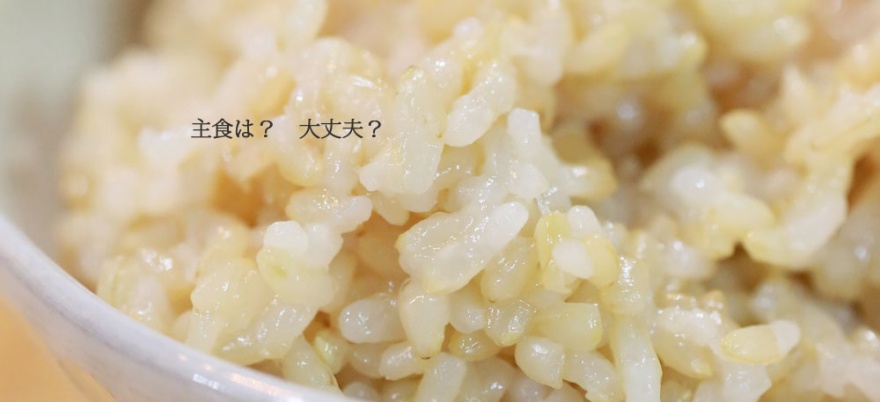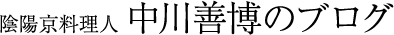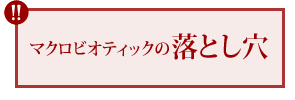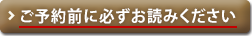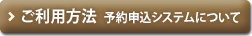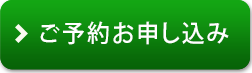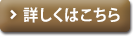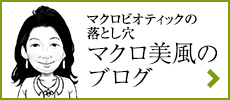ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)
- 小豆玄米投稿2026 Azさん(157-1)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 1月
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月
- 自由人コース2 12月の復習 Kiさん(81-2)
- 小豆玄米投稿2026 Hoさん(3-3)
- 自由人コース5 1月の復習 Saさん(31-1)
- 小豆玄米投稿2026 Yaさん(121-4)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月
- 幸せコース1月の復習 Niさん(17-8)
- キッズクラスの復習 Haさん(29-4)
- 「第9回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」1月17日
- 自由人コース6 12月の復習 Saさん(21-9)
- 自由人コース5 12月の復習 Saさん(84-2)
- 自由人コース6 12月の復習 Ohさん(15-10)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第17期 幸せコース 1月
- 幸せコース12月の復習 Niさん(17-8)
- 幸せコース12月の復習 Saさん(64-5)
- 自由人コース6 12月の復習 Hoさん(3-3)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第3期自由人コース3 1月
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第11期 秘伝コース 1月
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第2期 自由人コース5 1月
- 「キッズクラス 冬休み」1月7日
- 「キッズクラス 冬休み」1月6日
- 自由人コース5 12月の復習 Haさん(12-10)
- おせち投稿2025-2026 Yaさん(123-3)
- 丙午 氏神様に初詣 下御霊神社
- あけましておめでとうございます
- おせち投稿2025-2026 Itさん(113-1)
- おせち投稿2025-2026 Saさん(21-9)
最近のコメント
- 自由人コース6 12月の復習 Ohさん(15-10) に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月 に nakagawa より
- 小豆玄米投稿2026 Hoさん(3-3) に nakagawa より
- 自由人コース5 1月の復習 Saさん(31-1) に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第17期 幸せコース 1月 に nakagawa より
- 幸せコース12月の復習 Niさん(17-8) に nakagawa より
- 幸せコース1月の復習 Niさん(17-8) に nakagawa より
- 自由人コース6 12月の復習 Ohさん(15-10) に ゆき より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に ゆき より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 5期 自由人コース2 1月 に まりりん より
- 小豆玄米投稿2026 Hoさん(3-3) に おはる より
- 自由人コース5 1月の復習 Saさん(31-1) に つむぎ より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第17期 幸せコース 1月 に Ni (17-8) より
- 幸せコース12月の復習 Niさん(17-8) に Ni (17-8) より
- 幸せコース1月の復習 Niさん(17-8) に Ni (17-8) より
- キッズクラスの復習 Haさん(29-4) に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に nakagawa より
- 「キッズクラス 冬休み」1月7日 に nakagawa より
- 自由人コース5 12月の復習 Saさん(84-2) に nakagawa より
- 「第9回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」1月17日 に nakagawa より
- 自由人コース6 12月の復習 Saさん(21-9) に nakagawa より
- 「キッズクラス 冬休み」1月6日 に nakagawa より
- 幸せコース12月の復習 Saさん(64-5) に nakagawa より
- キッズクラスの復習 Haさん(29-4) に kyoro より
- 自由人コース6 12月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 1月 に おはる より
- 「キッズクラス 冬休み」1月7日 に ばんび より
- 自由人コース5 12月の復習 Saさん(84-2) に 朝 より
- 「第9回 中川式小豆絹玄米ごはんの炊き方教室(少量炊き含む)」1月17日 に おはる より
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2026年1月
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
- 2004年11月
- 2004年7月
カテゴリー
- 塾長の技 包丁使い (5)
- 塾長の技 鱧骨切り (3)
- 塾長の技 桂剥き (2)
- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)
- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)
- 塾長の技 料理動画 (5)
- シリット 圧力鍋の使い方 (3)
- 料理教室むそう塾 (2,839)
- 中川式玄米の炊き方指導 (4,526)
- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)
- 塾生さんの桂剥き (2)
- 塾生さんの包丁使い (6)
- 漬け物 (222)
- 技術 technique (9)
- 今日の復習 (7,472)
- 出し巻き投稿 (921)
- 桂剥き道 (3,869)
- YouTube集 (23)
- Silit製品販売 (25)
- KMS なかがわ (472)
- 京都 (201)
- Mac iPhone iPad (78)
- 料理 (69)
- 和え物 (146)
- 汁物 (103)
- sakana (6)
- 焼物 (139)
- 煮物 (393)
- 蒸し物 (22)
- 麺類 (154)
- 油物 (45)
- 炒め物 (10)
- 酢物 (20)
- 飯物 (132)
- 拘り (114)
- 思い (118)
- 甘い物 (194)
- 今日の瑠璃茄子2012 (24)
- 瑠璃茄子への道 (130)
- へびろて (2)
- マクロビオティック (94)
- アグリ (80)
- ソトメシ (21)
- レジニススム (31)
- 京まくろび (340)
- 今日の弁当。 (145)
- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)
- Tプラス販売 (5)
- 善右衛門的。cafe (84)
- 未分類 (612)
- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)
- 写真 Photographed (7)
- おせち投稿 (79)
- おせち投稿2018-2019 (23)
- おせち投稿2019-2020 (26)
- おせち投稿2020-2021 (26)
- おせち投稿2021〜2022 (25)
- おせち投稿2022-2023 (25)
- おせち投稿2023-2024 (36)
- おせち投稿2024-2025 (34)
- おせち投稿2025-2026 (30)
- 塾生さん鱧骨切り (607)
- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)
- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)
musooyajiのtweet
-
「中川式玄米の炊き方指導」カテゴリーアーカイブ
今日の宿題提出
みなさんこんばんは。 美味しい玄米を食べていますか?
今夜は色彩がもたらす味覚への影響をNiさんの投稿を使わせて頂いて少しお話しをてみましょうか?
金沢のNiさん(4-13)です。
Niさんはかなりお上手になられました。 お送りくださった玄米の画像がこれです。

どうですか? 一見して、ブログをご覧の方は「それほど美味しそうじゃないじゃん」と思っているのではないでしょうか?
しかしです。私にはそうは見えません。 元気に旨そうです。
本当はNiさんが実際に食べておられる玄米はこんな色をしているはずなのです。
Niさん、違いますか? コメントお待ちしております。

どうですか? 実に旨そうでしょ?
じつはこの2枚はまったく同じ画像です。 2枚目は私が画質調整をしました。
これが色彩がもたらす味覚への影響です。
面白かったでしょうか?
ご意見、コメントお待ちしております。
次は東京のIwさん(2-17)です。
540の米に580の水ですから 粒感のある炊きあがりに納得ですね。
ササニシキの限界までもちもち感が出ています。
もっともちもちさせたい場合はコシヒカリ系にされると手っ取り早いです。

かなりのオトコメシになっています。 原因は最初の攻撃的加圧が2分多いからです。
次回は580米に620水で 前半8分後半16分、蒸らし24分(保温の工夫要)で炊いてみてください。 次の投稿をお待ちしております。
カテゴリー: 中川式玄米の炊き方指導
5件のコメント
今日の宿題提出
みなさんこんばんは。 美味しい玄米を食べていますか。
今夜から日本は冷えそうです。 正しく玄米を食べて居る人は急激な季節の変化にも身体が驚くことはなく、スムーズに対処していけます。 風邪をひかないですね。
皆さんも医療費0を目指して美味しい玄米食を実践しましょう。
最初は神奈川のMiさん(5-9)です。
初めての投稿です。
玄米とは別に特別デモンストレーションで作った塩昆布をすごく美味しいとほめて頂きました。
ありがとうございました。 ぜひご自分でも作ってみてくださいね。

4.5リットルで4合炊くと、120%の水では少し多いかも知れませんね。 お好みの問題ではありますが。 大きく焦げていなければこの炊きあがりは旨いのではないでしょうか。 中間と最後の8分の火加減をうんと絞って、消さない程度に火をあてて下さい。
次は男性Suさん(3-7)です。

前回よりさっぱり炊けているということは浸水時間がたりないように見えます。
何時間水に漬けられてたのでしょうか?
前半の強火は下げずに後半の火加減を少し上げてみるとよいでしょう。
これからは真ん中の8分がキーになってきます。 タオル蒸しは有効ですね。
ある程度もちもちしながらふっくらと炊くのが難しいですが旨いですね。
目指してください。
次は名古屋のMuさん(5-1)です。
平和の4.5リットルをお使いです。
 平和の鍋はどうしてももちもち過多に炊けてしまいますが、うまく中川式にあてはめて炊かれています。 平和の鍋をお使いの方には参考になるでしょう。
平和の鍋はどうしてももちもち過多に炊けてしまいますが、うまく中川式にあてはめて炊かれています。 平和の鍋をお使いの方には参考になるでしょう。
真ん中の8分をもう少し火加減強めて炊いてください。 もっとぱりっとした仕上がりになります。
平和の圧力鍋の使い方の新しいスタンダードの鍵を見つけた気がしますね。
次は鳥取のSaさん(5-3)です。
もっちり感を増すには前半の火加減を強めることです。
 講習でお話したことをよく思い出してくださいね。 硬いのは浸水時間が足りないせいですね。 水も115まで増やせるでしょう。
講習でお話したことをよく思い出してくださいね。 硬いのは浸水時間が足りないせいですね。 水も115まで増やせるでしょう。
と、いってももうこの鍋は使われないのでしょうからまた新しく試行錯誤がはじまりますね。
がんばってください。
カテゴリー: 中川式玄米の炊き方指導
5件のコメント
今日の宿題提出
みなさんこんばんは 美味しい玄米を食べていますか。
毎日たくさんの方が投稿されて、それを私が診断して私なりのアドバイスを書き添えています。
しかし、それだけならば個別にメールに返信してアドバイス差し上げれば良いのです。
なぜ、皆様の目に触れるように記事にするのか? ここが大事なのです。
「人の振り見て我が振り直せ」という言葉もあるように、ここに出てくる玄米の炊きあがりに似た炊け方しか出来ずに悩んでいる方の参考になるわけです。
もちろんむそう塾の塾生さんだけの世界ではありません。 このブログをご覧くださっている方もご意見やご感想をお気軽にコメントくだされば有難いです。そして塾生さんたちの励みにもなります。 宜しくお願い致します。
それではじっくり見て参りましょう。
今夜は少なく3名の投稿でした。
まず最初はSaさん(5-14)です。
焦げ付いていた圧力釜を綺麗に再生されての炊飯です。
 その道具に手をかけてあげた分ちゃんと道具は良い仕事をしてくれていますね。 新しく釜を購入されても古い方を大事にしてあげて下さいね。 お願いします。
その道具に手をかけてあげた分ちゃんと道具は良い仕事をしてくれていますね。 新しく釜を購入されても古い方を大事にしてあげて下さいね。 お願いします。
基本的にSaさんは炊飯時間を間違えて覚えておられますね。 最初8分の攻撃的加圧のあと、弱火にして24分ではありません。 16分で良いのです。 トータルで24分です。
蒸らしも24分急速に鍋の温度が下がらないように蒸らしてください。
次はJoさん(2-14)です。
スキレットのような薄いタイプの圧力鍋で炊かれています。

これは何時間浸水されているのでしょうか? よく膨れていますね。
最初の加圧時に恐いほど蒸気が出るのはやはりダメですね。 少し弱めてください。
焦げが出来るのは後半の火加減が重要な鍵を握っています。
ということはJoさんは全体的に火加減を下げなければなりません。お試しください。
蒸らしは20分ではなく30分行って下さい。 美味しくなります。
滑り込みで投稿は鳥取のSaさん(5-3)です。
大きな鍋で少量を炊くという難しさを承知で頑張られました。

土鍋のような炊きあがりは空間が大きいために攻撃的加圧が不足しているためです。
歯に皮が挟まるのは明らかに浸水時間が長すぎるためです。講習の時には浸水時間の事もお話ししたはずです。 思い出してくださいね。
残念ながら私はもう玄米は失敗しないのですが(笑) もし炊き間違いをしたときはおじやかリゾットにします。 リゾットに関しては過去に婦人誌に載ったものを参考にしてください。
カテゴリー: 中川式玄米の炊き方指導
7件のコメント
楽しくて愉しくて仕方がありません 感謝です

蟹穴はどうかな? 湯気はどうかな? 焦げはどうかな?
みなさんの目が小さな鍋に集中します。 楽しい一瞬です。
貴方も蓋を開けたときの香りを嗅ぎに来られませんか?
最初は大阪のTeさん(2-8)です。
上手に炊かれるようになりました。 最初の投稿の玄米からすると別人が炊いたようです。

毎日食べても毎日美味しい玄米ですね。 ご苦労様でした。
ぶれないように。 忘れないように。
次は長崎県のTaさん(2-9)さんです。
メールにありましたが、最後の8分にガスマットを使用してももちもち感には関係はありません。
ふっくら感に関係するのです。 もともち感を司るのは最初の8分間だと言うことをお話したはずです。 思い出してくださいね。
 小さい鍋ですからはっきりとした蟹穴は見つけにくいかもしれません。
小さい鍋ですからはっきりとした蟹穴は見つけにくいかもしれません。
上手に炊きあがっていますから大丈夫です。
次はFuさん(4-8)です。
前回と構図がかなり違うのではっきり判りませんが、白米の硬さに近づいてきたのではないでしょうか。
 一般の方はよく噛んで食べてはくださいません。 ですから最初は白米のように食べられる硬さ、弾力で炊ける方が良いのです。
一般の方はよく噛んで食べてはくださいません。 ですから最初は白米のように食べられる硬さ、弾力で炊ける方が良いのです。
何分ぐらい炊いて何分ぐらい蒸らしておられるのか書いてありませんので想像でお話していますことをご了承下さい。
次は千葉県のHiさん(5-7)です。 さっそく投稿下さいました。

古米を同割で強い目の火で炊くとこうなります。
次回は後半の火をもっと弱めて、水を115にしてください。 コロッと変わります。
変化を楽しんでくださいね。
次は兵庫県のMiさん(4-2)です。
もう少し硬い目にすると皮が気にならなくなります。

次は中盤後半の火加減も少しだけ強くしてみてください。 オトコメシにするのです。
噛みごたえが変わります。 お試しください。
まだ少し優しすぎますね。お人柄が出ているのでしょう。
カテゴリー: 中川式玄米の炊き方指導
10件のコメント
むそう塾 終了しました

たくさんのご参加を得て、むそう塾第三回を行うことができました。
ご参加下さいました皆さん、本当にありがとうございました。
今回はいつもの玄米の炊き方に加えて常備菜として「しおこんぶ」の炊き方を
覚えて頂きました。
ありがとうございました。
感想やご意見、今後の要望など何でもお気軽にコメント下さい。
宜しくお願い致します。
むそう塾 中川善博 マクロ美風
カテゴリー: 中川式玄米の炊き方指導
8件のコメント