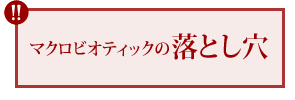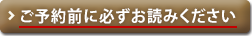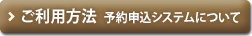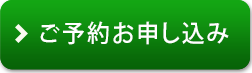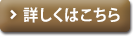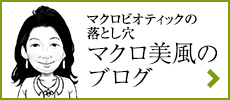美味しそうに出来ています。 色移りも発生していないですね。 合格です
美味しそうに出来ています。 色移りも発生していないですね。 合格です
ぴょんと立った絹さやは太いから麺やあらめと絡まないのです。 細く揃えて刻む練習をしましょう。



ブログ内を検索する
-
最近の投稿
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第2期 自由人コース5 12月
- 中川式バターカステラ
- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月
- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日
- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(21-9)
- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3)
- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10)
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)
- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9)
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)
- 年越しそば(晦日そば)を発売します 2025
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日
- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日
- 自由人コース2 11月の復習 Kiさん(81-2)
- 秘伝コース 11月の復習 Saさん(142-3)
- 満足コース11月の復習 Koさん(136-1)
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4)
- 自由人コース2 11月の復習 Itさん(113-1)
- 鱧骨切り特訓講座の復習 Itさん(113-1) 鱧納め
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 11月
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第6期 自由人コース1 12月
- 秘伝コース 11月の復習 Hoさん(100-1)
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第12期 満足コース 11月
- 自由人コース5 10月の復習 Saさん(84-2)
- 自由人コース5 11月の復習 Saさん(31-1)
- 小豆玄米投稿2025 Saさん(139-1)
- 満足コース10月の復習 Saさん(139-1)
- 2025年 塾長鱧納め 11月20日
- 幸せコース11月の復習 Niさん(17-8)
最近のコメント
- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1) に nakagawa より
- 幸せコース11月の復習 Yaさん(155-1) に Ya より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に 京子 より
- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10) に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に nakagawa より
- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3) に nakagawa より
- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日 に nakagawa より
- 自由人コース6 11月の復習 Saさん(15-10) に ゆき より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に ゆき より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 12月 に おはる より
- 自由人コース6 11月の復習 Hoさん(3-3) に おはる より
- 「おうちレストラン 第2弾」12月6日 に まりりん より
- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9) に nakagawa より
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に nakagawa より
- 満足コース11月の復習 Moさん(33-9) に ここ より
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に kyoro より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に ひかる より
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に nakagawa より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より
- マクロビオティック京料理教室 むそう塾 第1期 自由人コース6 11月 に nakagawa より
- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日 に nakagawa より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に nakagawa より
- 「おせちの苦手克服講座 魚編」 11月29日 に nakagawa より
- 秘伝コース 11月の復習 Saさん(142-3) に nakagawa より
- 自由人コース1 12月の復習 Haさん(29-4) に kyoro より
- 「おうちレストラン 第2弾」11月30日 に メロン より
アーカイブ
月別アーカイブ
- 2025年12月
- 2025年11月
- 2025年10月
- 2025年9月
- 2025年8月
- 2025年7月
- 2025年6月
- 2025年5月
- 2025年4月
- 2025年3月
- 2025年2月
- 2025年1月
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
- 2011年8月
- 2011年7月
- 2011年6月
- 2011年5月
- 2011年4月
- 2011年3月
- 2011年2月
- 2011年1月
- 2010年12月
- 2010年11月
- 2010年10月
- 2010年9月
- 2010年8月
- 2010年7月
- 2010年6月
- 2010年5月
- 2010年4月
- 2010年3月
- 2010年2月
- 2010年1月
- 2009年12月
- 2009年11月
- 2009年10月
- 2009年9月
- 2009年8月
- 2009年7月
- 2009年6月
- 2009年5月
- 2009年4月
- 2009年3月
- 2009年2月
- 2009年1月
- 2008年12月
- 2008年11月
- 2008年10月
- 2008年9月
- 2008年8月
- 2008年7月
- 2008年6月
- 2008年5月
- 2008年4月
- 2008年3月
- 2008年2月
- 2008年1月
- 2007年12月
- 2007年11月
- 2007年10月
- 2007年9月
- 2007年8月
- 2007年7月
- 2007年6月
- 2007年5月
- 2007年4月
- 2007年3月
- 2007年2月
- 2007年1月
- 2006年12月
- 2006年11月
- 2006年10月
- 2006年9月
- 2006年8月
- 2006年7月
- 2006年6月
- 2006年5月
- 2006年4月
- 2006年3月
- 2006年2月
- 2006年1月
- 2005年12月
- 2005年11月
- 2005年10月
- 2005年9月
- 2005年8月
- 2005年7月
- 2005年6月
- 2005年5月
- 2005年4月
- 2005年3月
- 2005年2月
- 2005年1月
- 2004年12月
- 2004年11月
- 2004年7月
カテゴリー
- 塾長の技 包丁使い (5)
- 塾長の技 鱧骨切り (3)
- 塾長の技 桂剥き (2)
- 塾長の技 だし巻き玉子 (1)
- 塾長の技 包丁砥ぎ (1)
- 塾長の技 料理動画 (5)
- シリット 圧力鍋の使い方 (3)
- 料理教室むそう塾 (2,825)
- 中川式玄米の炊き方指導 (4,521)
- 塾生さんのだし巻き玉子 (19)
- 塾生さんの桂剥き (2)
- 塾生さんの包丁使い (6)
- 漬け物 (222)
- 技術 technique (9)
- 今日の復習 (7,453)
- 出し巻き投稿 (921)
- 桂剥き道 (3,869)
- YouTube集 (23)
- Silit製品販売 (25)
- KMS なかがわ (472)
- 京都 (200)
- Mac iPhone iPad (78)
- 料理 (69)
- 和え物 (146)
- 汁物 (103)
- sakana (6)
- 焼物 (139)
- 煮物 (393)
- 蒸し物 (22)
- 麺類 (154)
- 油物 (45)
- 炒め物 (10)
- 酢物 (20)
- 飯物 (132)
- 拘り (114)
- 思い (117)
- 甘い物 (194)
- 今日の瑠璃茄子2012 (24)
- 瑠璃茄子への道 (130)
- へびろて (2)
- マクロビオティック (94)
- アグリ (80)
- ソトメシ (21)
- レジニススム (31)
- 京まくろび (340)
- 今日の弁当。 (145)
- 塾生のお弁当 卒業作品 (4)
- Tプラス販売 (5)
- 善右衛門的。cafe (84)
- 未分類 (611)
- 珈琲・コーヒー・Coffee (50)
- 写真 Photographed (7)
- おせち投稿 (79)
- おせち投稿2018-2019 (23)
- おせち投稿2019-2020 (26)
- おせち投稿2020-2021 (26)
- おせち投稿2021〜2022 (25)
- おせち投稿2022-2023 (25)
- おせち投稿2023-2024 (36)
- おせち投稿2024-2025 (34)
- 塾生さん鱧骨切り (607)
- 小豆玄米炊飯の炊き方指導 (72)
- 煮物コース基礎力強化桂剥き (214)
musooyajiのtweet
-


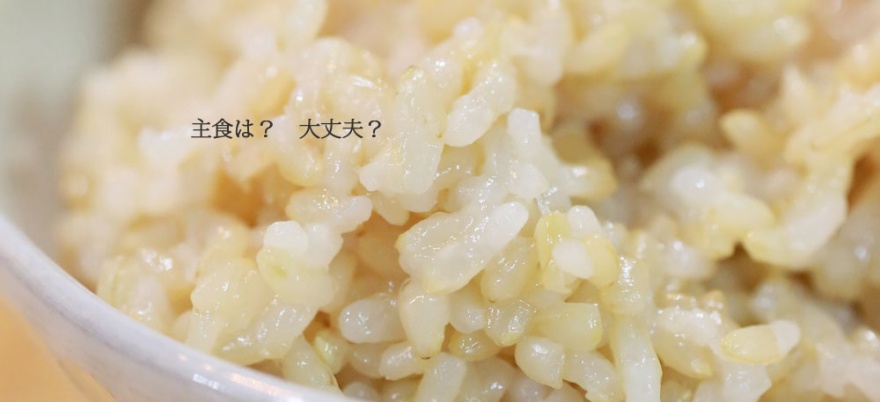
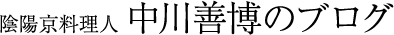



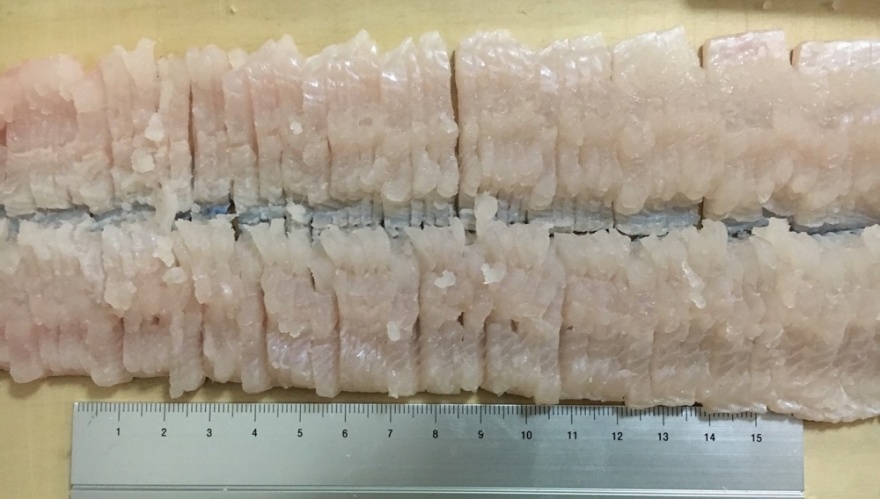

 落としの花が咲いていませんね。 湯引きの仕方を間違っているのかな?
落としの花が咲いていませんね。 湯引きの仕方を間違っているのかな? 美味しそうに出来ています。 よく染みています。万願寺も茄子も良い発色で仕上げられています。盛り付けも良いです 合格です
美味しそうに出来ています。 よく染みています。万願寺も茄子も良い発色で仕上げられています。盛り付けも良いです 合格です 感じを掴んでいますね 合格です 万願寺かズッキーニを天近くにおきましょう。
感じを掴んでいますね 合格です 万願寺かズッキーニを天近くにおきましょう。 上手にできているのですが ピンぼけです しっかりピントを合わせて大きな画面で確認してからメール添付しましょう
上手にできているのですが ピンぼけです しっかりピントを合わせて大きな画面で確認してからメール添付しましょう
 美味しそうに出来ています。 自衛隊色にならずによく染み込んでいます。 合格です
美味しそうに出来ています。 自衛隊色にならずによく染み込んでいます。 合格です